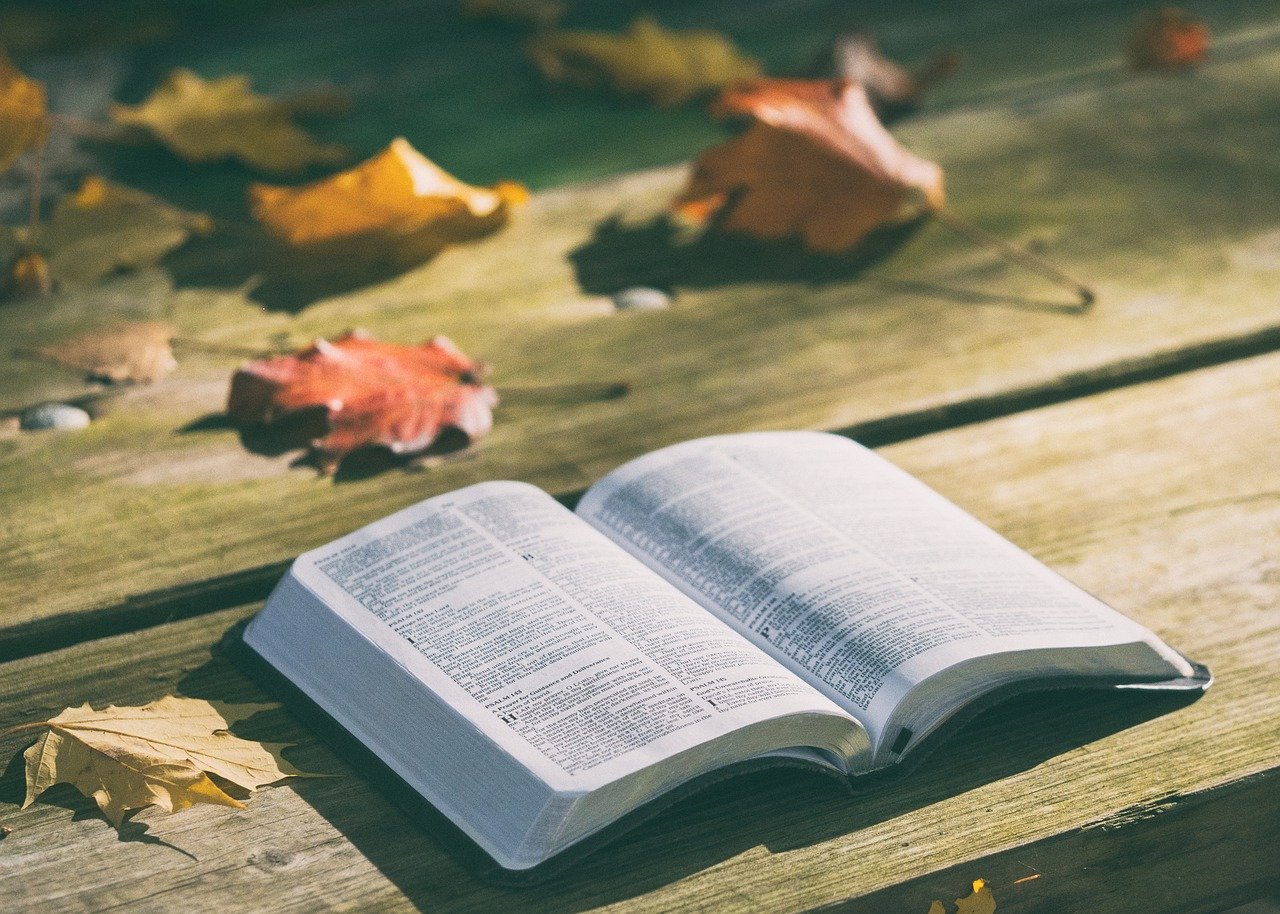 経済
経済 知識社会に向けて – 神野直彦『人間回復の経済学』
読書案内神野直彦『人間回復の経済学』(2002)市場経済に従属する人間 1982年から87年の足掛け6年に亘った中曽根政権は、構造改革を主導し、規制緩和、民営化、行政改革を推し進めた。しかし、その結果の90年代は、「失われた10年」と呼ばれ...
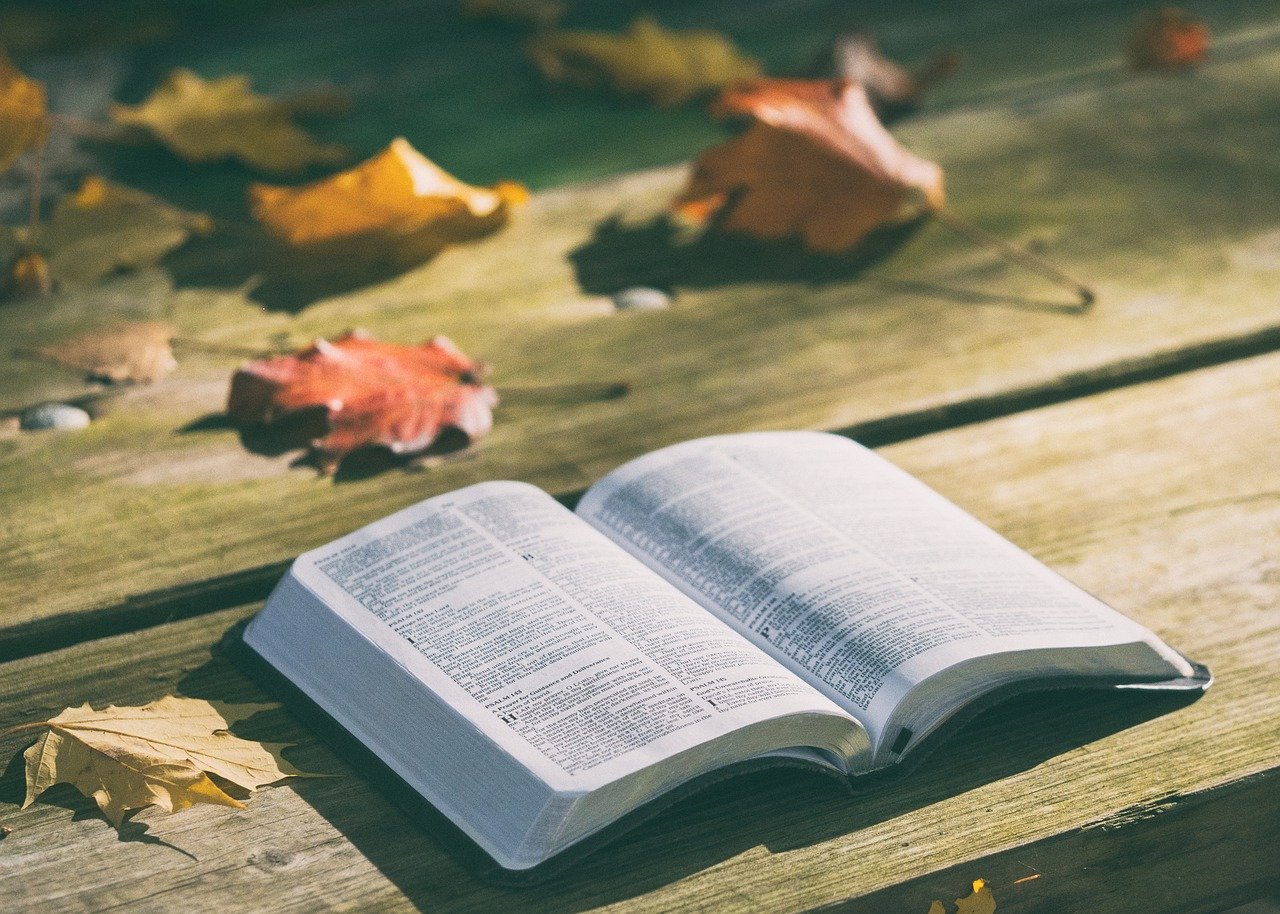 経済
経済  経済
経済  経済
経済  経済
経済  経済
経済 .jpg) 経済
経済  経済
経済  経済
経済  経済
経済  経済
経済 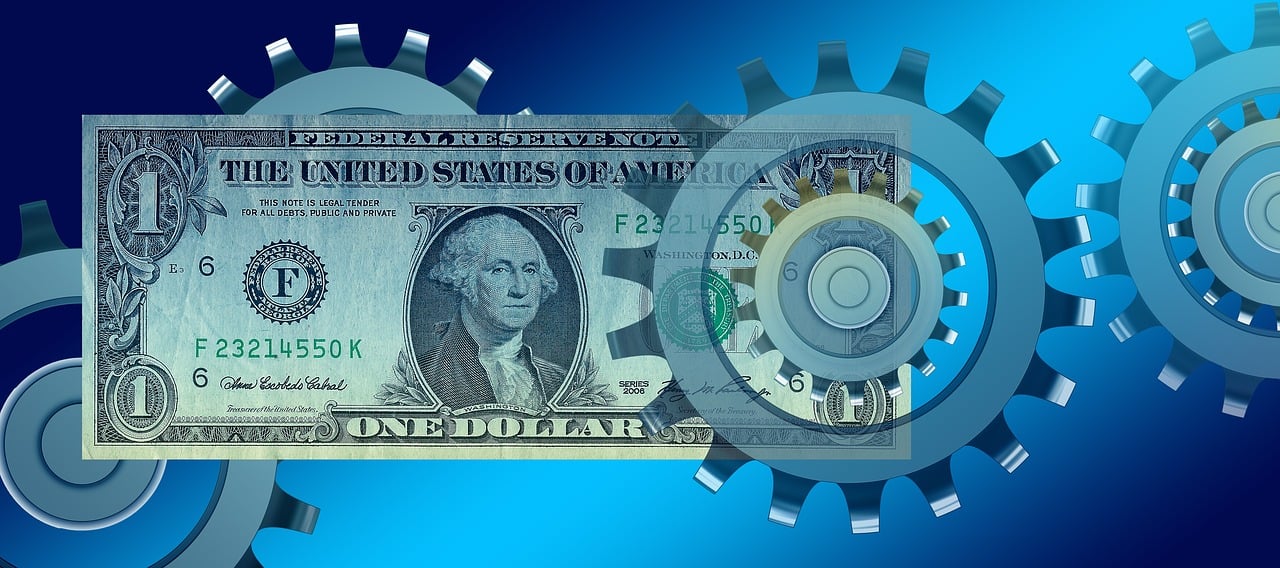 経済
経済  経済
経済