為替レートを決める要因とは?
現金を使わず、金融機関を通じて資金のやり取りを行う仕組みを「為替」といいます。特に、国外との取引において異なる通貨を交換する場合は「外国為替(外為)」と呼ばれます。外国為替市場では、通貨と通貨の交換比率である「為替レート」が常に変動しています。
この為替レートは、基本的に通貨の「需給関係(需要と供給のバランス)」によって決まります。では、その需給関係を変動させる具体的な要因には、どのようなものがあるのでしょうか。以下に代表的な要因を紹介します。
貿易収支
国際間の物やサービスのやり取りに伴い、代金の決済が行われます。その過程で通貨の交換が必要となるため、国際貿易は外国為替市場における実需の取引(実際の取引に基づく需要)を反映しているといえます。
たとえば、ある国の輸出が増えれば、外国企業はその国の通貨で代金を支払う必要があるため、その通貨への需要が高まります。逆に輸入が多い場合は、自国通貨を売って外国通貨を購入する必要があるため、自国通貨が売られることになります。
このように、貿易収支が黒字(輸出超過)であれば通貨高、赤字(輸入超過)であれば通貨安になる傾向があります。
金利差
金利が高い国では、より高い利回りを求めて資金が流入しやすくなります。投資家は高金利の国の通貨を買って預金や債券に投資するため、その通貨の需要が高まり、結果として通貨高につながります。
一方、金利が低い国では、資金がより有利な金利を求めて国外へ流出しやすくなり、通貨安の要因となります。
このように、高金利は通貨高、低金利は通貨安となる傾向が見られます。一般に金利の高低はその国の通貨の強さ(為替レート)に直接的な影響を与える重要な要素です。
インフレ率の差
物価が継続的に上昇するインフレ傾向にある国では、通貨の購買力が低下するため、通貨の価値も相対的に下がります。つまり、通貨安につながるのです。
反対に、物価が下落するデフレの状況下では、通貨の購買力が高まり、通貨高になりやすくなります。
国家間でインフレ率を比較すると、一般的にインフレ率が高い国の通貨は安く、インフレ率が低い国の通貨は高く評価される傾向があります。
実質金利差
実質金利とは、名目金利から予想されるインフレ率を差し引いて算出される金利です。これは投資家が実際に得られる「実質的な利回り」を示しており、為替市場でも重要な判断材料となります。
名目金利だけを見るのではなく、インフレ率を考慮に入れた実質金利の方が、より実態に即しているため、中長期的にはこの実質金利の差が為替レートに大きな影響を与えることになります。
実質金利が高い国では通貨高、低い国では通貨安の傾向が見られます。
まとめ
為替レートは、複数の経済的要因によって変動する動態的な指標です。貿易収支、金利差、インフレ率、実質金利差といった要素はいずれも通貨の需給に直接的な影響を及ぼす重要な要素であり、為替市場を理解するうえで欠かすことのできない視点となります。
これらの要因を総合的に捉えることで、為替相場の動向をより正確に読み解くことができるでしょう。
参考
岩田規久男『デフレと超円高』(2011)
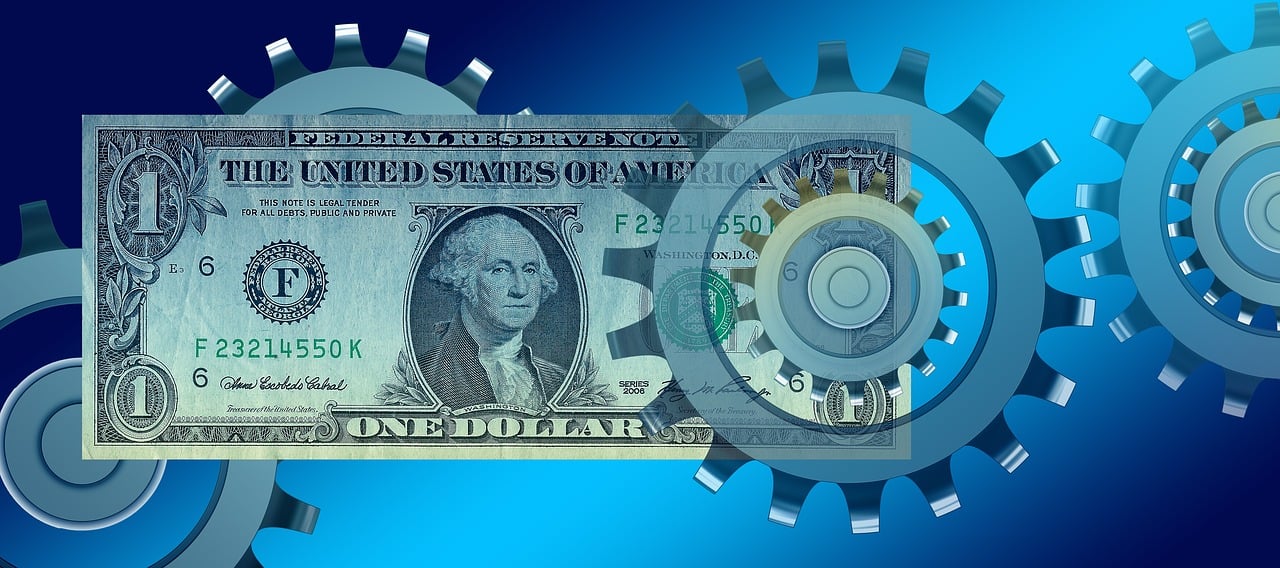

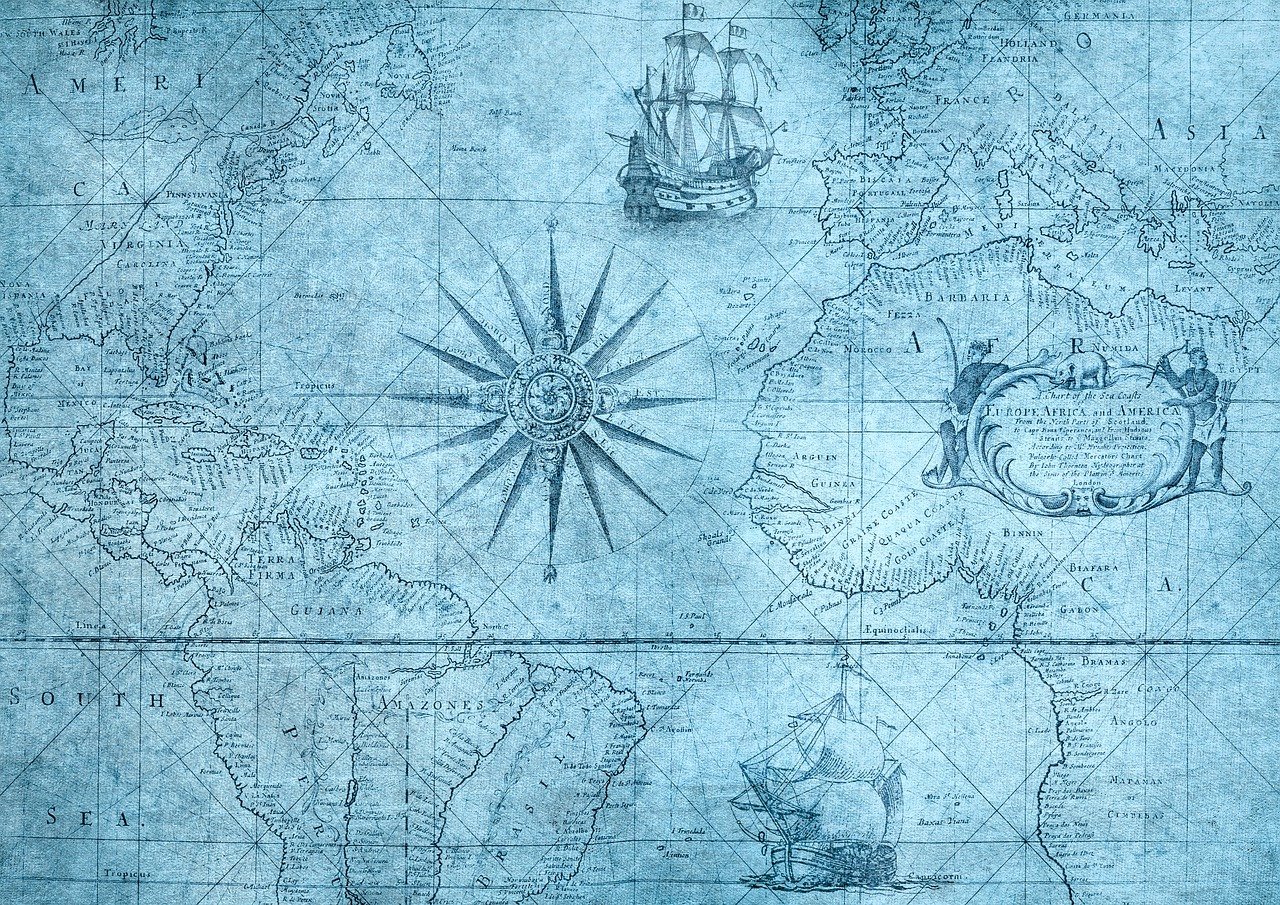

コメント