東京医科大学不正入試事件
東京医科大学の不正入試問題が波紋を広げている。
7月4日、文部科学省政策局長だった佐野太容疑者が、受託収賄の疑いで逮捕された。報道によれば、東京医科大学を文科省の私立大学支援事業の対象校に選定する見返りとして、佐野容疑者の息子を同大学に不正に合格させたとされている。
現在までに明らかになっている主な事実関係は以下のとおりである。
- 東京医科大学の臼井理事長や鈴木衛学長ら、合否判定に関与する複数の幹部が、佐野前局長に対し事業選定を働きかけ、その見返りとして息子の合格を取り計らったとされる。
- 両者の接触は、医療コンサルタント会社役員・谷口浩司容疑者を仲介として行われていた。
佐野容疑者は昨年5月までに計3回、当時医療コンサルタント会社役員だった谷口容疑者の設定で臼井氏と3人で会食。この中で臼井氏は平成28年度に東京医科大が「私立大学研究ブランディング事業」の対象校に選定されなかったため、29年度は選定されるよう申請書の書き方の助言を求めた。佐野容疑者は文字を大きくすることや図表を入れることなどを助言したという。
その際、佐野容疑者は医学部志望の息子について「東京周辺の医大に入れたいが、どこがいいか」と尋ね、臼井氏が東京医科大を薦めたところ「一番行きたいと思っているのでよろしく」と発言したという。
・東京医科大学の不正入試は、複数年に亘り、組織的に行われていた疑惑が浮上。佐野容疑者の受託収賄事件は、氷山の一角との見方が濃厚に。
関係者によると、入試担当課長は数年前の就任直後、臼井前理事長から「裏口入学があるから承知しておいてほしい」などと告げられたという。不正合格の実務などを、前任者から聞くよう前理事長に指示されたといい、今年度の不正にも携わった可能性がある。
・東京医科大学同窓会が、合否判定の優遇を求める受験者のリストを過去に作成していたことが発覚。
複数の関係者によると、同大では卒業生を経由して同窓会などが、合否判定での優遇を求める受験生の親族らの依頼を集約。リスト化して大学幹部に伝えていたという。
ある同大関係者は取材に「合否判定ではリストの記号に従って加点された。◎は『絶対頼む』、○は『可能なら』、×は『加点不要』という意味で、臼井前理事長の指示だった」と話した。
・2次の小論文、面接試験のみならず、1次の筆記試験の段階から、佐野容疑者の息子だけでなく、複数の受験生に対して、不正が行われていた。
東京医科大学(東京)が今年2月に実施した入試の1次試験で、複数の受験生の試験結果のデータが改ざんされ、点数が加点されていたことが関係者の話でわかった。東京地検特捜部は、大学のパソコンなどを「デジタル・フォレンジック(DF)」で解析。受託収賄容疑で逮捕された同省前局長・佐野太容疑者(59)の息子を含む複数の受験生に対する不正を確認した。
関係者によると、佐野容疑者の息子が受験した同大医学科の一般入試では、数学・理科・英語のマークシート方式(数学の一部を除く)で1次試験を実施。合格ラインに達した受験生が小論文などの2次に進み、両方の試験結果を合算して合否が決まった。1次の採点は同大が委託する外部業者が行い、試験結果を電子データで同大に戻していた。
不正入試と「医者の子は医者」の構図
医学部への裏口入学―――
今回の事件を受けて、あらためて浮かび上がるのが、医学部入試をめぐる透明性への疑念である。東京医科大学に限らず、「医学部では不正な合格操作が行われているのではないか」という疑念は、かねてから指摘されてきた。
こうした疑念の背景には、「医者の子供は医者になることが多い」という社会通念がある。特に開業医の場合、子が親の医院を継ぐという話はよく聞かれる。
この現象を、単に「医師家庭には経済力があり、子供を医学部に進学させやすいから」と説明することも可能だが、教育格差という観点から考えると、もう少し複雑な要因がある。経済的余裕がある家庭ほど、教育環境を自由に選べるため、職業選択の幅が広がるはずである。にもかかわらず、一定の職業に偏る傾向があるのは、教育機会や評価の公正性に何らかの歪みが生じている可能性を示唆している。
今回のように、試験の公正性が損なわれる事態は、その象徴的な表れとも言えるだろう。
東京医科大学と縁故入学の問題
受験関係者の間では、東京医科大学が縁故による入学が多い大学として知られていたという指摘もある。今回の事件は、そうした疑念を裏付けるような内容でもあり、大学側の入試運営に対する信頼を大きく揺るがすものである。
関係者によると、かつて同大で行われていた「裏口入学」は2次試験で半ば公然と加点されていたという。今回の事件は前例のない1次試験での加点で、前理事長らが極秘裏に不正合格を進めた実態が浮かぶ。
東京医科大のある現職教授は、こう証言する。かつては定員120人中、半分以上が医者の子供だったが、近年は約20人、うち約10人は同大出身者だという。
今後、同様の問題が他大学に波及する可能性も含め、入試制度全体の透明性と公平性を見直す必要があるだろう。
面接・小論文による“調整”と試験制度の透明性
医学部の入試において、面接や小論文を含む2次試験で“ゲタを履かせる”(=得点を上乗せする)といった対応が行われるケースがあることは、以前から一部で指摘されていた。今回の事件により、こうした実態が表に出たことは、受験制度の公平性に対する信頼を大きく揺るがす結果となった。
実際、受験関係者の間では、「面接評価は調整の余地が大きい」との認識が共有されているようであり、場合によってはそれを当然視する意見も見受けられる。中には、2次試験での縁故的な調整を正当化する声さえあるという。
参考
・裏口入学を高須克弥院長が告白「入学金も半額にまけてくれた」 – Livedoor News
問題の核心:筆記試験(一次試験)にまで及ぶ不正
しかし、今回の事件で特に深刻なのは、2次試験だけでなく、1次試験の筆記試験においても不正が行われていた点である。
読売新聞などの報道によれば、東京医科大学では、複数の受験生のマークシートの点数データが不正に改ざんされていたという。しかも、同大学では採点業務を外部業者に委託していた。仮に大学側が業者に改ざんを指示していたとすれば、組織的な不正の可能性が高く、より重大な問題である。
さらに、「今年だけの出来事なのか」「過去にも同様の操作があったのではないか」といった疑問が残る点も見逃せない。今回の事件が氷山の一角に過ぎないとすれば、入試制度の根幹そのものが問われる事態となる。
“特別枠”制度と不透明な選抜の懸念
加えて、東京医科大学では、1次試験を免除する「特別枠」とされる入試制度が存在していたことも明らかになっている。この制度の詳細は不透明であるが、その存在自体が制度の公平性に対して疑問を呼ぶ。
「特別枠」による合格者の中には、政治家の子息を含むとされるケースもあるとの報道がある。制度設計そのものが縁故的な関与を許す余地を持っていたとすれば、それは不正や恣意的な運用の温床となる可能性がある。
「佐野前局長の逮捕後、永田町では自民党のA議員の名前が話題になっています。A議員の子供が東京医大の入試で“ゲタ”を履かせてもらったようだというのです」(永田町関係者)
「子供が東京医大に入学したのは事実。しかし、現在、特捜部が捜査している『不正入学』とは全く無関係です。子供は、高校時代の成績を基にした『特別枠』の選考試験を受け、入学を果たした。今回の事件では1次試験で『加点』があったとされていますが、『特別枠』での選考は1次試験を経るものではありません。だから、そもそも不正入学の対象ではあり得ませんよ」
A議員の複数の親族が東京医大の関係者だという。それが疑われる理由のひとつになっているのかもしれない。
こうした制度の運用実態について、大学側には明確な説明責任が求められるだろう。
医師の資質と入試制度の関係
今回の不正入試疑惑が事実であるとすれば、受験本来の学力基準を満たしていないまま、医学部に入学している学生が一定数存在している可能性があるということになる。医師は人命を預かる職業であり、高い専門性と責任感が求められる。そのため、入試における公正性や学力の担保は、極めて重要な前提条件である。
一方で、医師として実際に就業するためには、最終的に国家試験に合格する必要がある。このことから、「仮に入試に不正があったとしても、国家試験に合格していれば一定の能力はあるはず」と考える人も少なくないだろう。
しかし、現実には医師国家試験の合格率は毎年90%を超えており、2017年度(平成29年度)には東京医科大学の合格率が97.1%に達している。国家試験は、6年間の専門教育を経た学生を対象に、基本的な医学的知識と臨床判断力を確認するための試験であり、選抜というよりは「最終確認」の性質が強い。
このことは、医師になるまでの過程において、最も厳しい選抜が行われているのは入試の段階であることを意味している。実際、東京医科大学医学科の2018年度の受験者数は3,535人、合格者数は214人であり、倍率は16.5倍という極めて高い競争率であった。
つまり、医学部入試は医師への道を大きく左右する“実質的な関門”であり、だからこそ、その過程における公正性や透明性が極めて重要だと言える。不正入学が問題視されるのも、この「入口」の選抜が医師としての将来を決定づけている構造に由来している。
こうした問題に対しては、現役の医師からも「医療の質を維持するには、入試制度の信頼性を確保すべき」との声が上がっており、今後の制度的な見直しや再発防止策が強く求められている。
「裏口で入っても、国家試験だってあるんだし、そういう人は医者になれないのでは?」
そうとばかりは言い切れません。医師の場合、医学部に入学し、卒業したら「医者になる」ことをかなりの確率で確約されているようなものなのです。たとえそれが、同業の医師から見て「えっ、この人大丈夫?」という知識レベルの人でも……。
文部科学省の私立大学支援事業をめぐる、東京医科大学の裏口入学問題。汚職容疑で逮捕された前科学技術・学術政策局長の佐野太容疑者の長男は、一次試験から加点されていたとも報じられた。国立大学の医学部を卒業し、現在総合病院で生活習慣病を専門とする医師の小田切容子さんは、勉強不足の人がお金で医師になりうることもある医学部の現状を嘆く。
問われる大学の統治機構
大学の組織運営体制は、一般的に閉鎖的な性格を持ち、外部からの監視やチェックが入りにくい傾向がある。今年明らかになった日本大学の理事会をめぐる問題では、大学運営の在り方が社会通念とかけ離れていることが強く批判されたが、東京医科大学においても、理事長であった臼井氏に権限が過度に集中し、適切なガバナンスが十分に機能していなかった可能性が指摘されている。
報道などで伝えられている関係者の証言からは、臼井前理事長の強い影響力のもとで組織運営が行われていた実態が浮かび上がっており、その体制が不透明な意思決定や不正の温床となっていた可能性もある。
同大のある元教授は、臼井前理事長が学長になった際のエピソードとして「東京医科大は同窓会の力が強かったので、教授会の存在感を示すための『改革の旗手』として臼井さんを送り込んだ。そうした意味では学内で期待された人材だった」と話す。
別の大学関係者は「下が提案しても、『これでいく』とはねつけるワンマンタイプ」と評する。今年に入って臼井前理事長の意向で、これまで2期6年だった理事長の任期に関する定款は3期9年に延長されたという。
また、官僚との利権構造を作り上げることで、学内での自らの権力基盤を維持しようとしていたのではないかという見方もある。たとえば、文部科学省の佐野前政策局長の息子が不正に入学した見返りとして、東京医科大学が同省の私立大学支援事業の対象に選定され、約3,500万円の助成金(税金)を受け取ったとされている。
皮肉にもこの助成金(血税)は「私立大学研究ブランディング事業」に対して支払われるものだった。ある意味、東京医科大学が一躍有名になったことだけは確かだが……
臼井氏は当時、一部委員に裏口入学リストを渡していたとされる。2次試験後の入試委員会の場で臼井氏が、リスト掲載者の小論文の点数について「この点数はちょっと違うんじゃないか」と声を上げると、意向を察した入試委員が「そうですね」と同調し、点数が加算されたという。
ある大学元幹部は、臼井氏が異例のやり方で不正合格を主導した動機をこう推し量った。「われわれにとって文科省は“神”。局長どころか課長でも学長自らが出迎えるほどだから」
医療現場の信頼回復に向けて
本件で問われているのは、単に官僚による収賄や大学側の不正といった個別の事件にとどまらない。より根本的な問いとして、「医師という職業に就くにあたって、その資質や適性が公正に評価されているのか」という社会的な信頼の基盤が揺らいでいる点にある。
多くの医師が真摯に学び、誠実に職務を果たしているのは事実であり、医療従事者に対する社会の敬意はその努力の積み重ねによって支えられている。しかし同時に、少数ではあるが、資質に疑問のある医師や、制度の不備により不適切に資格を得た者が存在する可能性があることも否定できない。
今回のような事件は、医師個人の問題にとどまらず、医療制度全体に対する不信感を生む可能性がある。東京医科大学においては、過去の入試をあらためて検証し、不正が疑われる合格者については、事実関係を明らかにする必要がある。
報道によれば、今回の事件で明らかになった「合格者優遇リスト」には、大学関係者だけでなく、官僚や政治家に関係する人物の名前も含まれているとされている。今後の捜査の進展次第では、政界を巻き込む大騒動に発展する可能性もある。
東京医科大学は、東京地検の捜査に協力し自浄作用を働かせるのか、それともリストにある人々を庇って、さらなる「ブランド」の低下を招くのか。これまでの経緯に真摯に向き合い、自らのガバナンスの再構築に取り組む姿勢が求められる。
社会からの信頼を取り戻す第一歩として、まずは、すべての医師が正当な評価を経てその資格を得たという事実を明確にしなければならない。
信頼回復は、透明性と説明責任を伴った改革から始まる。
*引用文中の太字強調は、引用者

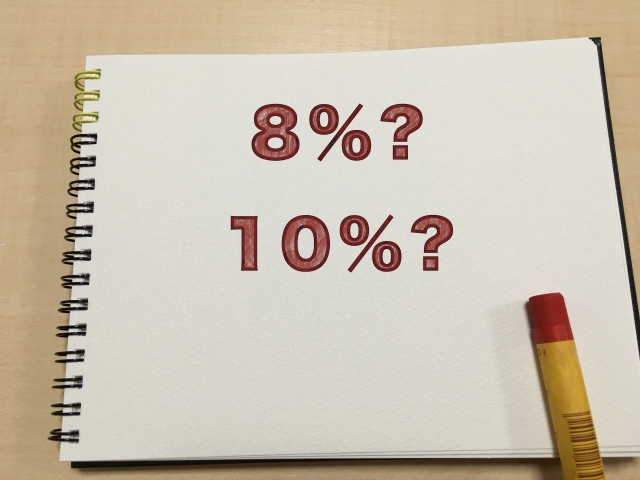

コメント