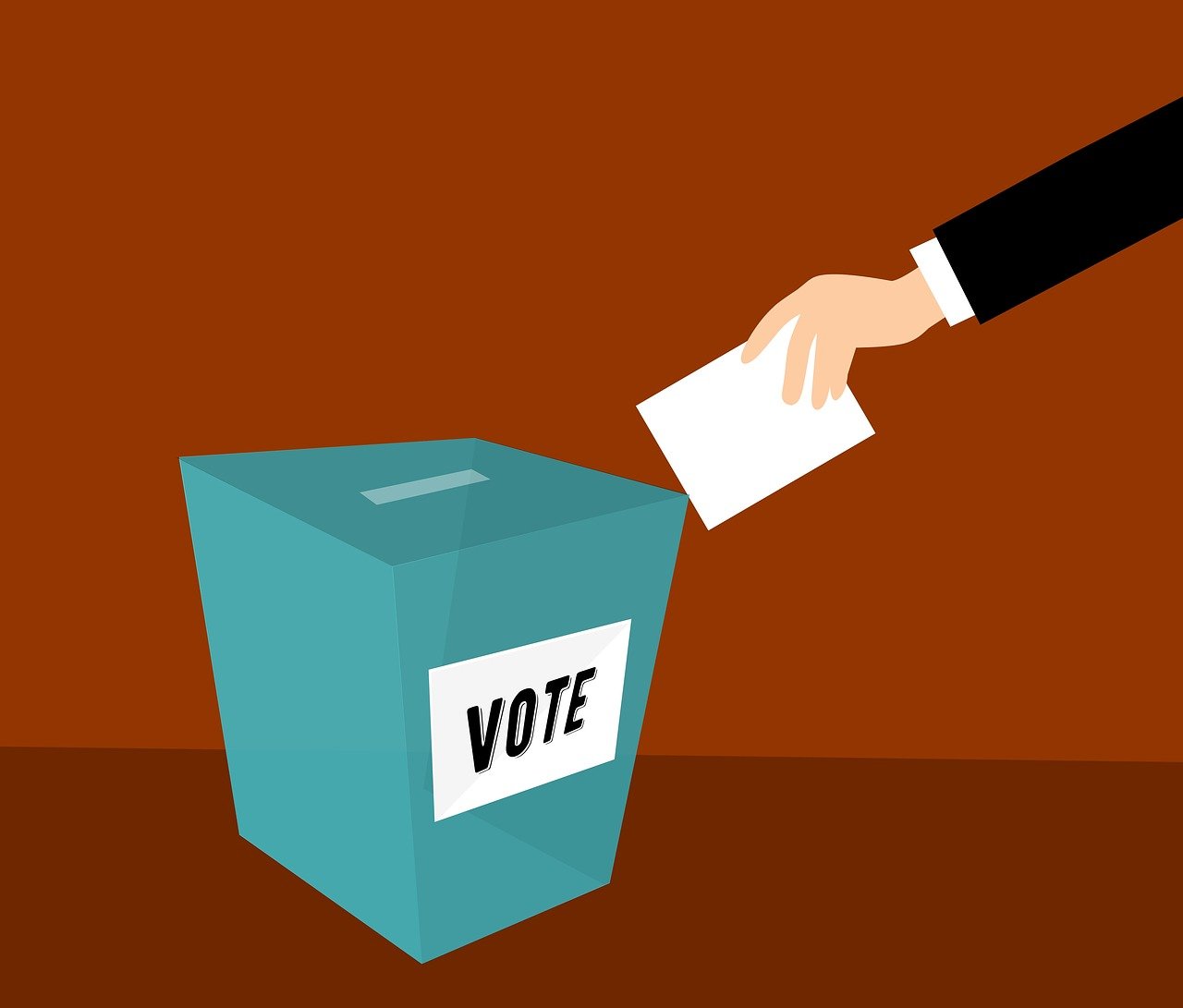 政治
政治 【選挙の仕組み】国政選挙とは? – 衆議院総選挙と参議院通常選挙
国政選挙とは 国政選挙とは、国政に関わる選挙のことで、国会議員を選出します。 日本の国政選挙は、衆議院と参議院の二院制に基づいて行われるため、衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙の二つがあります。それぞれの選挙制度について詳しく見ていきまし...
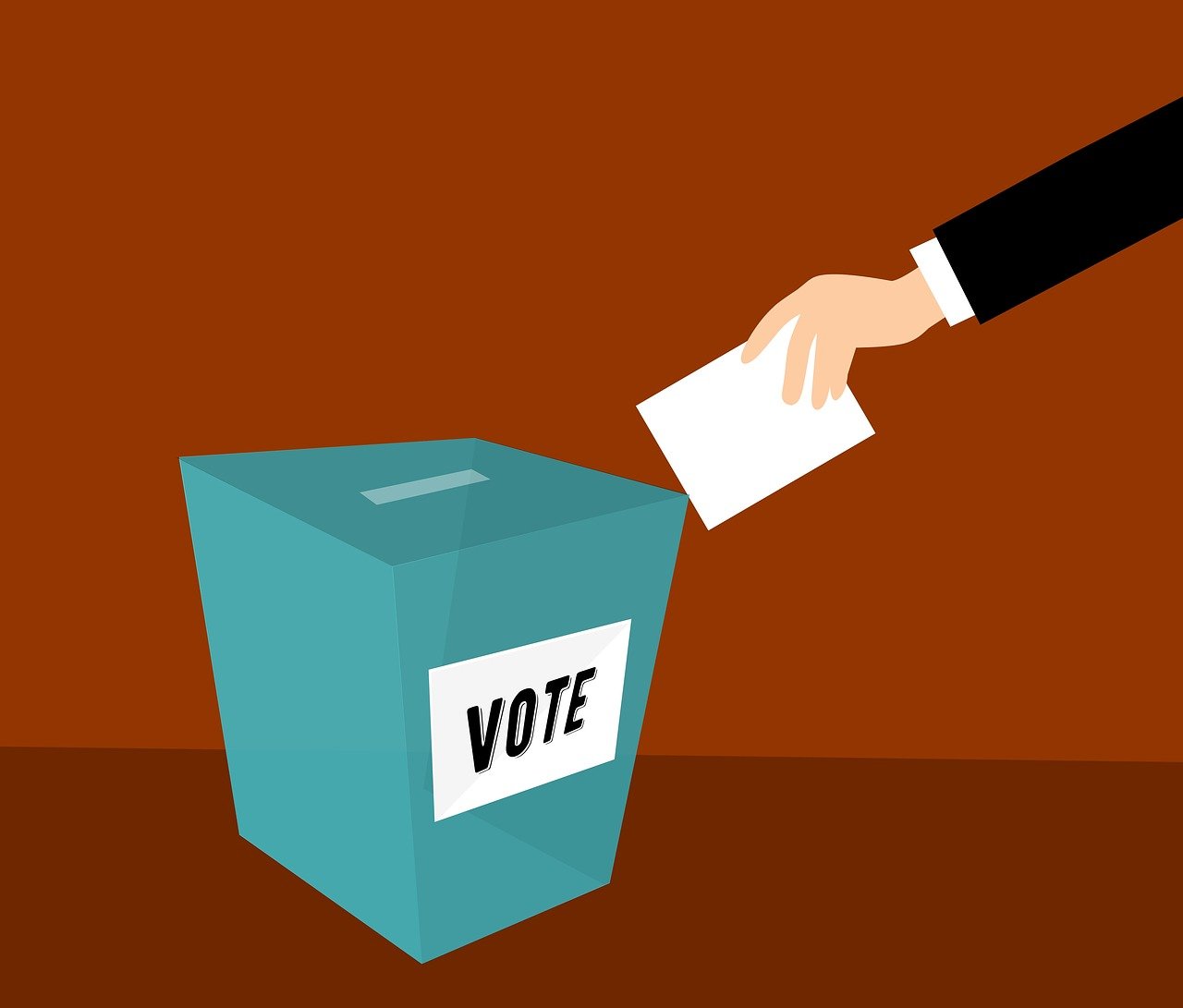 政治
政治  政治
政治  科学・技術
科学・技術  教育・学習
教育・学習 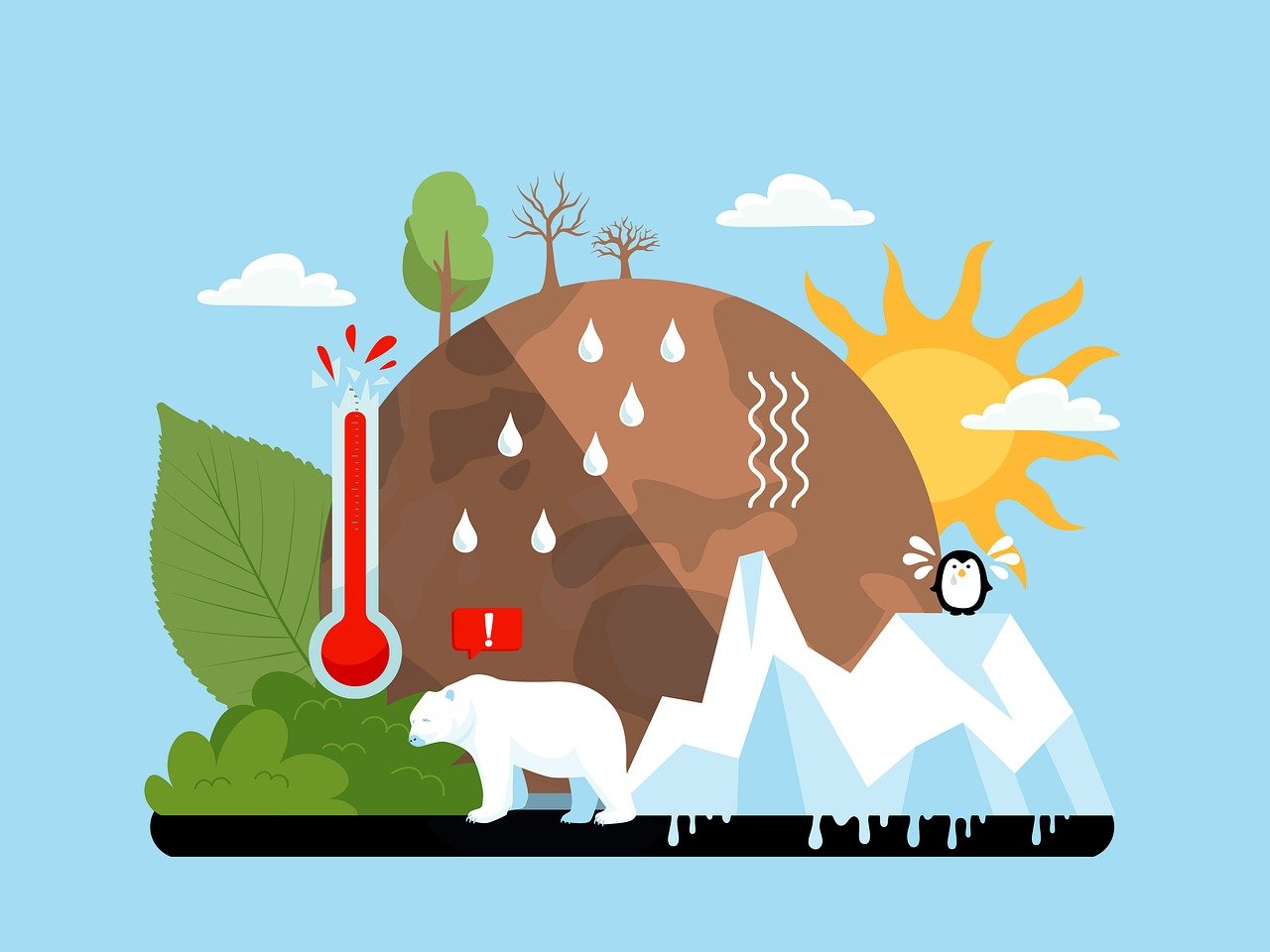 環境
環境  環境
環境  環境
環境  経済
経済 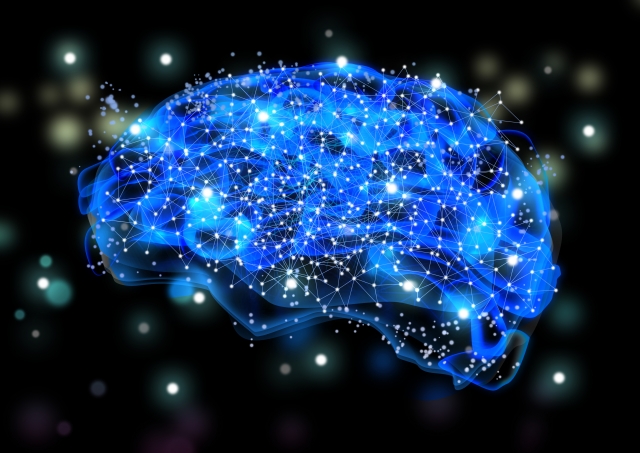 科学・技術
科学・技術  科学・技術
科学・技術  言葉・表現
言葉・表現  経済
経済