藤井聡『公共事業が日本を救う』(2010)
民主党政権への批判本
2010年に刊行された本。
2009年8月に民主党政権が誕生しているので。。。もう執筆動機がミエミエの「政治的」本。
当時、民主党政権が発足し、公共事業への予算削減が主要な政策課題として浮上していた。著者は、そのような状況において「公共事業はすべて無駄だ」という極端な議論が広がっているとし、それに警鐘を鳴らすと主張する。
ん?🤔
当時も今も公共事業のすべてを廃止しろなどとは誰も述べていない。(「2位じゃダメなんですか?」とは言っていたが。。。)
民主党政権の誕生に焦ったのか、公共事業予算を死守すべく、急ごしらえで本書を出版したという印象を拭いきれない。
なぜ民主党政権が成立したのか?
なぜ自民党が支持を失ったのか?
なぜ「事業仕分け」が政権の主要課題となったのか?
それは、自民党政権下の予算編成に、透明性も政策合理性もなかったからだ。
要するに、公共事業が国民からまったく信頼されなくなったのだ。
公共事業に対する最大の懸念は、利益誘導政治の温床になっているという点である。ハッキリ言って、それ以外に問題はない。問題の所在そのものは極めて単純だ。
民意を無視した一部の関係者によって、合理性や必要性を欠いた事業に対し、巨額の税金が投入されている。
したがって、こうした構造を見直し、限られた予算を合理的な政策に適切に配分できる仕組みを整えることこそ、公共事業を巡る最大の政治的課題である。
言い換えれば、政策決定において「いかに政策の合理性を確保するか」が問われているのだ。この課題を解決しない限り、公共事業に対する批判が消えることはない。
しかし、本書の著者はその核心には一切触れず、ただ「予算を削るな」と繰り返すのみである。
本書は、公共事業という権益を擁護するためだけに強引な議論を展開しているように見える。一例として、高速道路事業に関する主張を挙げよう。
高速道路事業をめぐる問題
まず、高速道路について。
著者は、日本では6車線以上の高速道路がわずか8%しかなく、3車線以下の狭い道路が約30%を占めていることを問題視し、これが慢性的な渋滞を引き起こしていると主張している。
しかし、日本のように緑被率が高く、可住面積も狭い国においては、道路の拡幅には地理的・環境的な制約がつきまとう。人口密度が低く土地に余裕のある諸外国と、日本を単純に比較するのは無理がある。
さらに重要なのは、渋滞の最大の原因は車線数ではなく「料金所の存在」であるという点だ。
例えば、ドイツのアウトバーンは完全無料であり、アメリカ、フランス、イギリスなどでも、高速道路の大部分は基本的に無料。料金所の存在自体が非常に少ない。
これに対し、日本では料金所が非常に多く、頻繁に足止めを強いられる。
したがって、渋滞の解消を図るのであれば、まずは料金所の廃止や、高速道路の原則無料化を検討するのが筋だろう。
ところが、著者は渋滞の原因として最も重要なはずの料金所には一切言及していない。なぜなのか?
それは、かつての道路公団をめぐる問題を調べてみると、なーんか分かってくる。
料金所で徴収された料金は、かつて「道路特定財源」として管理されていた。この財源は、国会審議を経る一般財源とは異なり、官僚が自由に使える裁量の余地が大きかった。その特定財源をめぐり、道路公団やその傘下の数千にのぼる外郭団体がずさんな運用をしていた事実が、小泉政権下で明るみに出て政治問題化した。
この道路公団とその外郭団体は、そのほとんどが官僚の天下り先であり、自民党の道路族議員との癒着関係が常態化していた。談合や随意契約が横行し、調査が進む中で複数の贈収賄事件も発覚した。
その結果、2005年に道路公団は民営化され、将来的な高速道路無料化が決定。さらに2009年には、ようやく道路特定財源が一般財源化された。
自民党の道路族議員と官僚は、道路公団を民営化することで問題の幕引きを図ったつもりなのだろうが、予算執行に関する本質的な問題はまったく変化していない。
料金所は依然として残され、徴収された料金は高速道路建設のための借入金返済に使われている。仮に国会審議を通ったとしても、その道路建設に合理性と経済効率が伴わなければ、永久に高速道路の無料化は実現しない。
民主党政権から安倍政権への政権交代を経て、再び予算編成の不透明さが目立ち始めている。そして、国民の関心が薄れるとともに、ほとぼりが冷めたといわんばかりに御用学者が暗躍しだす。
少なくとも、道路の維持管理に対してどのような財源がふさわしいのか、利用者負担の原則を前提とするなら、料金所以外にどのような負担の仕組みがあるのか。こうした基本的な問いから再検討すべきである。
そのような検証を一切行わず、ただ「予算は削るな」と叫ぶ姿勢は、学者として誠実さに欠けていると言わざるを得ない。
この本、一事が万事こんな調子。
どの章にも共通しているのは、官僚の権益を侵すような主張は慎重に避けているように見える、という印象である。
日本の都市計画に見る政治不在
日本の公共事業の問題点は、「都市計画」の分野で特に顕著に表れている。
本来、都市には明確な中心部があり、そこを起点に人や交通が計画的に動く構造であるべきだ。しかし、日本では都市計画がほとんど存在せず、どこが中心なのかすら曖昧な都市構造が多い。その結果、鉄道・地下鉄・バスの路線はバラバラで、全体の目的や方向性が見えない。
区画整理にも一貫性がなく、商業施設や住宅、風俗店などが無秩序に混在し、歴史的建造物の隣にパチンコ店が建つような場面も珍しくない。街並みや景観もひどく、見るに堪えない。
こうした歪んだ都市の姿は、もはや簡単に修正できる段階を超えている。本来、都市計画は政治と行政が強いリーダーシップを持って進めるべき公共事業だ。しかし現実には、政治家は自分の選挙区への利益誘導を優先し、計画性のない予算の奪い合いに終始している。都市全体を見据えた再開発ではなく、民間任せの局所的な再整備が中心で、都市全体の構造をどうするかという視点が欠けている。
理想的な都市では、中心部に機能を集約し、人が自然に集まる流れをつくる。そのために公共交通を整備し、逆に自家用車の流入を制限して渋滞を抑える。そして、都市は人口100万~300万規模ごとに一つの中心を持ち、それを単位として都市構造を組み立てるのが望ましい。欧米では、このような計画の下で都市が設計されており、日本との違いは一目瞭然だ。
日本の都市が使いにくく不便なのは、こうした計画性の欠如が原因である。地方都市ですら、車がなければ生活が成り立たない。公共交通と都市の構造が断絶しているからだ。藤井氏の留学体験を持ち出さずとも、海外の都市を少し見れば、日本の都市機能の欠陥はすぐにわかる。
生活環境も深刻だ。防災対策の遅れた密集住宅地、狭く高額な住宅、長時間の通勤・通学、改善されない満員電車、少ない公園や緑地、老朽化した校舎や橋梁──問題は山積している。最近では、放射性物質の除染という新たな課題まで加わっている。
都市の再開発は喫緊の課題である。たとえば、藤井氏も指摘していたように、防災や景観の観点から、都市部の電柱は地中化すべきだ。しかし、実際にはそれすらほとんど進んでいない。
なぜこうした問題が放置されるのか。それは、公共事業の決定プロセスそのものが根本的に間違っているからだ。公共事業が、本来の公共性ではなく、政治家の利益誘導や官僚の利権確保の手段として扱われているためである。
仮に、公共事業を財政政策として景気浮揚の手段とするのであれば、公共投資の波及効果が高い都市部を優先すべきである。だが現実には、投資効率の低い地方に多くの予算が配分され、1970年代型の「ハコモノ」事業が跋扈し、都市部の整備は後回しにされてきた。その結果、日本の都市部の生活環境は、先進国の中でも最悪の部類に属している。
(なお、地方に配分された巨額の公共事業予算も、結局は誰にも使われない巨大施設を建てるだけで、その後は赤字を垂れ流し、その損失は住民税で補填される、という構図に陥っており、地域の発展にもほとんど貢献していない。)
改めて強調したい。都市計画という公共事業ほど、政治が主導的役割を果たし、公共の利益の観点から推進されなければならない分野はない。公共事業を、官僚と族議員による既得権益の温床から切り離し、明確なビジョンと強力なリーダーシップのもとで実施できる制度設計を構築しなければ、公共事業への信頼は回復しないだろう。
必要な公共事業とは?
公共事業そのものは必要である。問題は、それをいかに合理的かつ公平な制度のもとで実行するかという点にある。
ところが藤井氏は、「公共事業は必要だ」という誰もが否定しがたい前提を出発点に、「だから予算削減は誤りである」「したがって公共事業はどんどんやるべきだ」と結論づける。まるでバカボンのパパも驚くような三段論法である。もしこのような議論を本気で展開しているのだとすれば、それは問題の本質を理解していないか、あるいは族議員や官僚の既得権益を守ろうとしているのか、そのいずれかだろう。
現在の公共事業は、景気浮揚効果に乏しく、財政を圧迫して政策の自由度を奪い、結果として財政危機を招いている。経済効率性を欠いたインフラ事業が、必要性の検証もないまま実行され、将来的な負担をすべて次世代に押し付けている。まさに救いようのない状況だ。
その結果、都市部の整備は後回しになり、経済の停滞は長期化、財政は破綻寸前となり、国民には増税が押し付けられている(消費税10%も、すぐそこだ)。
このような中で、公共事業に対する信頼を取り戻すためには、まず制度の見直しから始めるべきだ。ところが藤井氏の主張は、「公共事業は必要だ」という一点を強調するあまり、制度の根本的な欠陥には一切触れない。もしくは、意図的にそこを避けているようにすら見える。彼の議論は、現在の公共事業に対する批判的な視点を、慎重に言葉を選びながら巧妙に回避しているのではないかとすら思える。
消費税も、社会保障費も、国民の負担は増すばかりだ。これまで世界でも類を見ないほどの忍耐力を発揮してきた日本国民も、そろそろ限界に近づいている。この現実を、公共事業を私物化してきた官僚・族議員、そして御用学者たちは真剣に受け止めるべきである。
(……消費税が10%になり、高速道路無償化がさらに延期されるようなことがあったら、さすがに日本人も怒るだろう。たぶん……いや、そうであってくれ!)
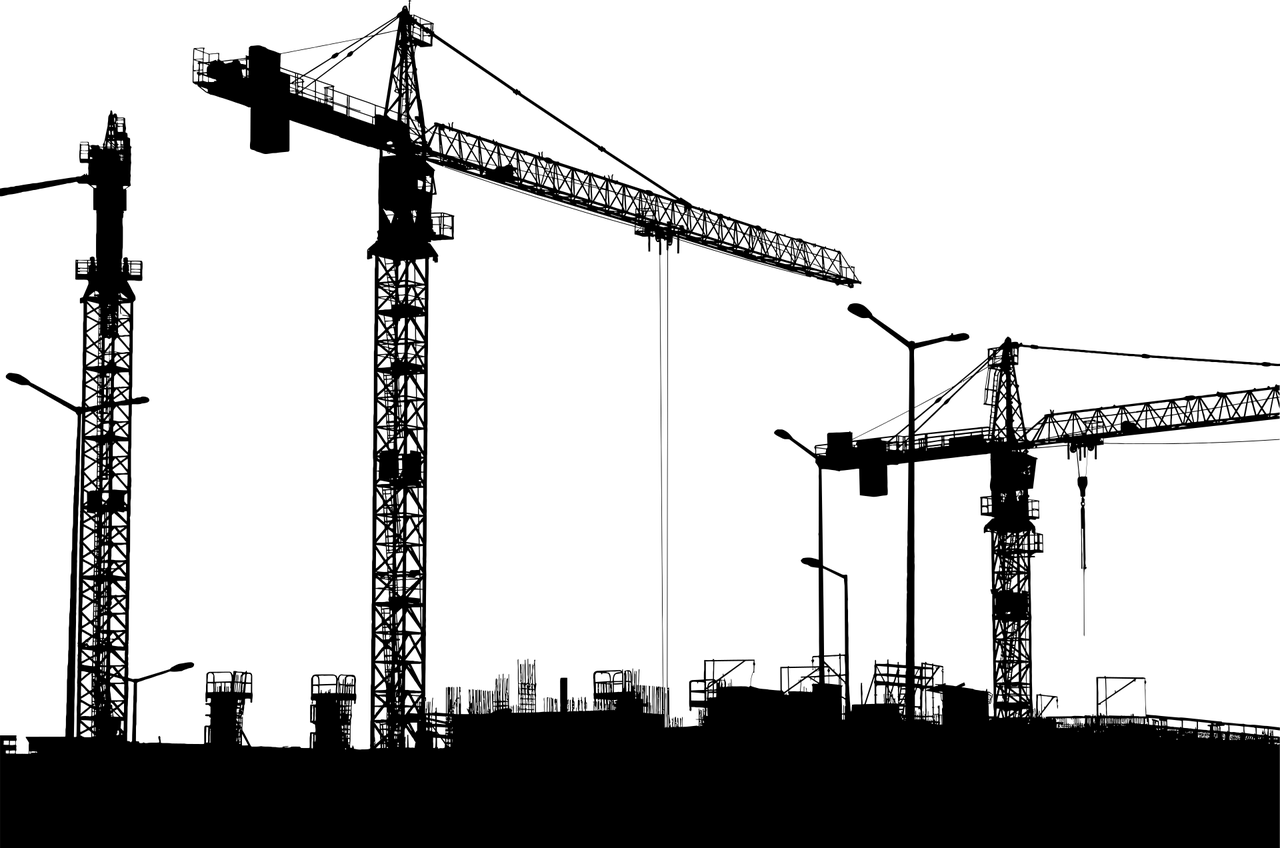
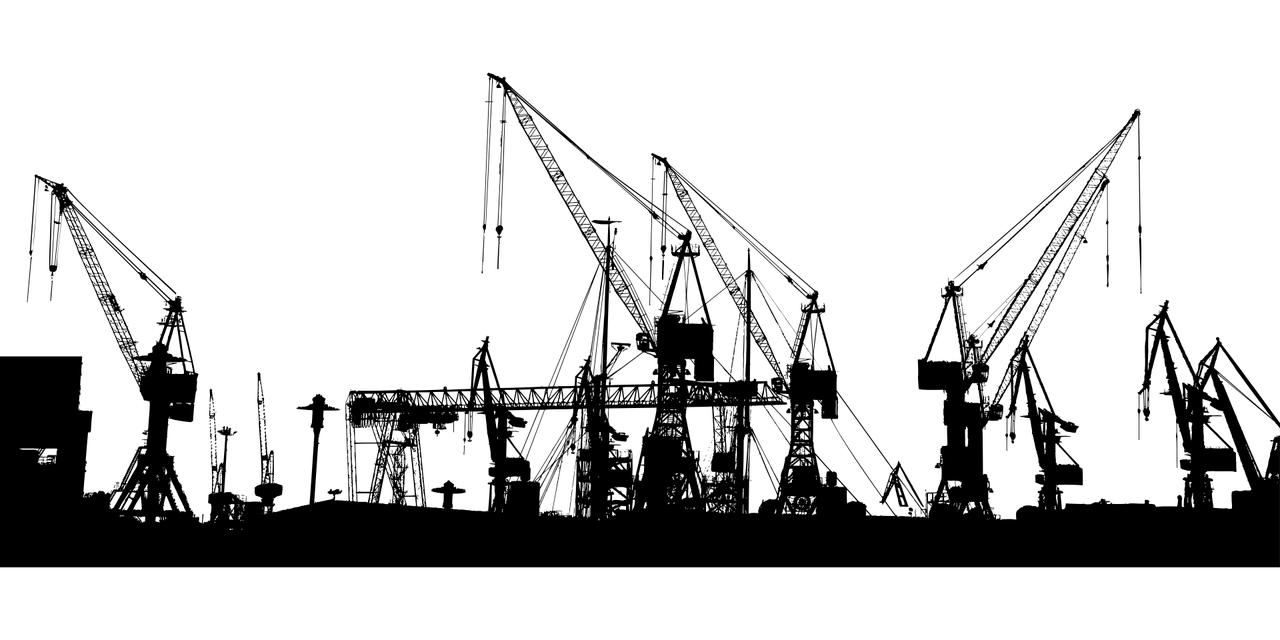

コメント