地球温暖化議論の始まり
科学的関心の起源
地球温暖化に関する科学的な関心は、19世紀末にまで遡る。1896年、スウェーデンの科学者スヴァンテ・アレニウスは、二酸化炭素(CO₂)の増加が地球の気温上昇を引き起こす可能性を初めて理論的に示した。彼は、化石燃料の燃焼によるCO₂の排出が、地球の気候に長期的な影響を及ぼすと予測した。
近代的な観測の始まり
地球温暖化の科学的調査は、1950年代末から本格的に始まった。カリフォルニア大学のロジャー・レヴェルとチャールズ・デービッド・キーリングは、1958年よりハワイのマウナロア観測所にて大気中の二酸化炭素(CO₂)濃度の精密な観測を開始した。1961年には、CO₂濃度が季節的な周期変動以外に、長期的に上昇していることを世界で初めて示した。彼らの調査結果から、CO₂が毎年2ppmほど増加していることが明らかとなった。
この観測は現在も継続されており、CO₂濃度は1958年の315ppmから2005年には381ppm、2018年には406ppmへと一貫して上昇している。この長期的なCO₂濃度の上昇曲線は、キーリングの名にちなんで「キーリング曲線」と呼ばれている。
この調査結果が重要なのは、CO₂濃度の上昇が産業革命以降の化石燃料の使用拡大と相関性を示しているからだ。
氷床コアに閉じ込められた気泡から過去のCO₂濃度が測定できるが、その調査結果から、完新世(紀元前9000年)から産業革命(1760年頃)が始まる前の二酸化炭素濃度は、280ppm前後で安定していたと推測されている。
政治的関心と国際的な取り組み
1979年、アメリカ国家科学アカデミーは「チャーニー報告書」を発表し、CO₂の増加が地球の気温上昇を引き起こす可能性を科学的に評価した。この報告書は、地球温暖化に対する政治的関心を高める契機となった。
1992年には、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)が採択され、1997年には京都議定書が締結された。これらの国際的な取り組みにより、地球温暖化は世界的な課題として認識されるようになった。
温室効果ガスの多様性と影響
CO₂は最も代表的な温室効果ガスであり、温室効果ガス排出量全体の約80%を占めている。大気中におけるCO₂濃度の上昇と気候変動には相関性があり、科学的に証明されている。現在、それを覆すような科学的調査は存在しない。もちろん、陰謀論を除いてである。
温室効果ガスはCO₂だけではない。他にもあり、それらもまた人為的な活動によって増加の一途を辿っている。
メタン(CH₄):大気中に存在するメタンの約60%は人為的な活動によるものである。主な排出源は、埋め立て地、化石燃料の燃焼、排水処理場、畜産場などである。大規模な畜産場では、液状厩肥をためるタンクからメタンが発生する。一方、家畜ではなく野生の動物から自然に排出された糞尿からはメタンは出ない。
CO₂に比べて温室効果が約25倍強いとされる。
亜酸化窒素(N₂O):農業における窒素肥料の使用や、工業活動、化石燃料の使用、森林や農業廃棄物の燃焼などが主な排出源である。
六フッ化硫黄(SF₆)およびペルフルオロカーボン(PFC):これらはアルミニウム精錬や半導体製造といった産業活動によって大気に排出される。人間の活動以外からは一切発生しない。
ハイドロフルオロカーボン(HFC):空調の冷媒として使われる。フロンガスの代替品として広まっている。
水蒸気:実は水蒸気にも温室効果がある。気温の上昇によって大気中の水蒸気の量が増えており、温暖化の悪循環を生み出している。
CO₂をはじめとしたこのような温室効果ガスの排出に伴って、一貫して気温は上昇し続けている。気候変動の影響は、世界各地で顕在化している。
正しい認識と正しい取り組みへ
地球温暖化は、19世紀末から科学的に議論されてきた問題である。科学的調査としては、60年以上の蓄積があり、科学的根拠に基づいる。科学的な正当性を議論する段階はとうに過ぎている。
20世紀後半からは国際的な政策課題として取り組まれている。現在では、温室効果ガスの排出削減や再生可能エネルギーの導入など、持続可能な社会の実現に向けた取り組みが求められている。
参考
アル・ゴア『不都合な真実』(2017)
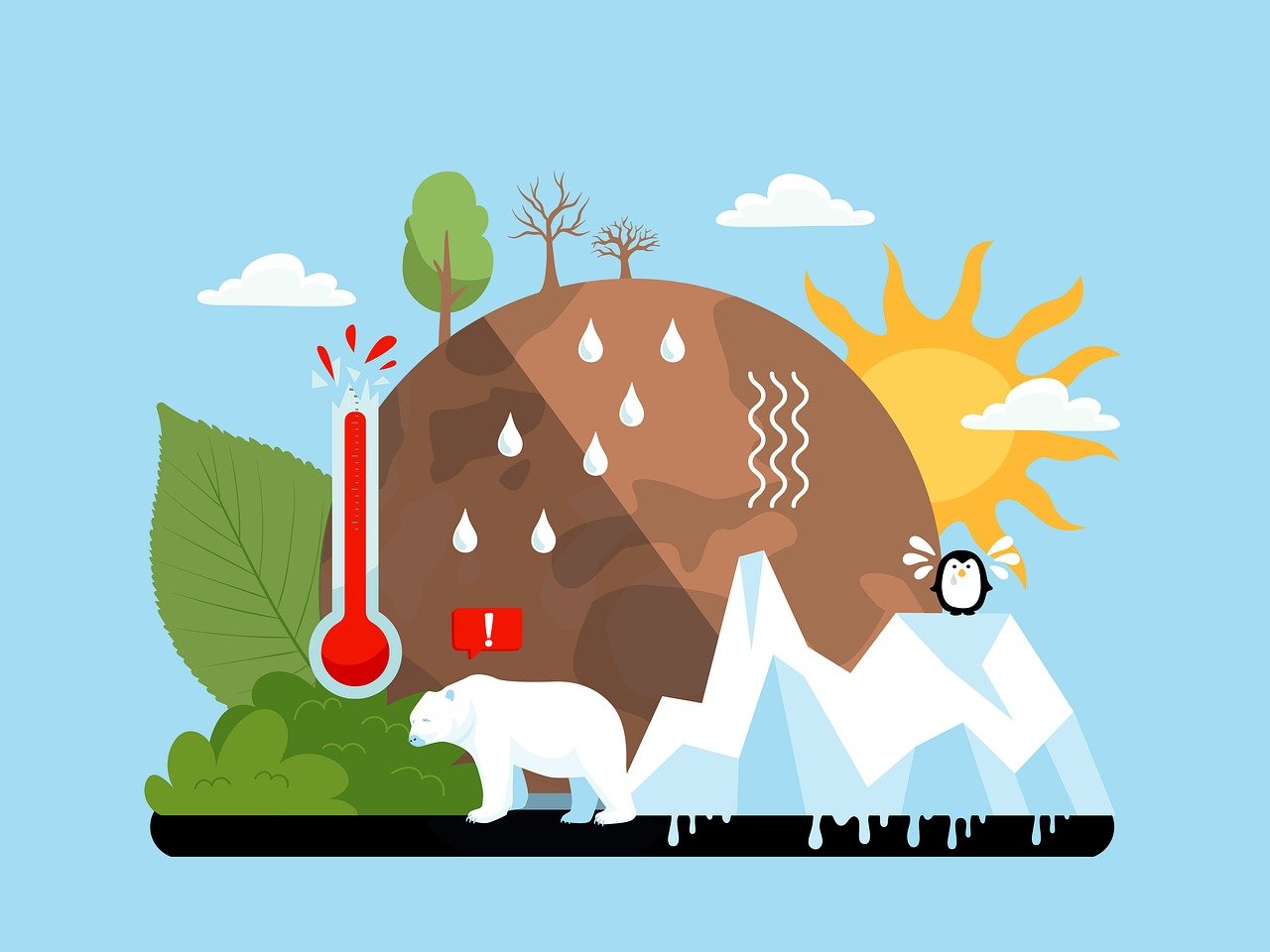


コメント