エマニュエル・トッド『シャルリとは誰か? – 人種差別と没落する西欧』(2016)
テロの衝撃とフランス社会の分断
2015年1月、パリにある風刺週刊紙シャルリ・エブド本社が、イスラム過激派と見られる犯人により襲撃され、12人が殺害された。この事件はフランス社会に大きな衝撃を与え、直後にはテロへの怒りと悲しみが全国的に広がった。
事件を受けて、フランス国内では「テロへの断固たる反対」と「シャルリ・エブドへの連帯」が強く叫ばれるようになった。多くの人々が「Je suis Charlie(私はシャルリ)」というスローガンを掲げてデモに参加し、それがまるでフランス人としての忠誠を示す証明のような雰囲気すら生まれた。
しかし、そのような反応には一面的な危うさも含まれていた。テロに反対することと、シャルリ・エブドの表現を無条件に支持することは、必ずしも同じではない。実際、犠牲者への哀悼の意を示しつつも、同紙の過激な風刺表現には賛同できないと感じる人々も少なくなかった。
とりわけ、イスラム系移民の人々にとっては、この事件が複雑な葛藤を生むものであった。彼らの一部は「Je suis Charlie」と公言し、フランス社会の一員としてテロに反対する立場を明確にした。しかし一方で、自らの信仰を侮辱する表現を行うメディアを支持せざるを得ない状況には、深い内面的ジレンマが伴っていたに違いない。
フランスにはライシテ(laïcité)と呼ばれる原則がある。公共の場に宗教色のあるものを持ち込むことを禁止する原則だ。この原則に基づいてフランスでは、宗教的慣習について、いくつかの法制化が行われている。2004年には、ブルカやヒジャブなどの公立学校での着用を禁止する法案が可決されている。
フランスで生きていくということは、宗教的信念を持った人々にとっては、自らの信仰とライシテの原則との間の葛藤を生きることを意味していた。今回の事件は、この葛藤の存在を改めて浮き彫りにさせた。
ライシテの変化
フランスは共和政の国家だ。国民を一つにまとめているのは、宗教でもなく、王族でもない。自由・平等・友愛というフランス革命の理念だ。
この理念のもとで、宗教は私的領域にとどめられ、公共空間では政教分離の原則である「ライシテ(laïcité)」が貫かれてきた。ライシテは、宗教と世俗のあいだに妥協を図る仕組みとして機能してきたのである。
テロとライシテの意味の転換
2015年のシャルリ・エブド襲撃事件は、ライシテと自由への挑戦と捉えられ、多くのメディアはこれを「表現の自由とライシテを守る戦い」と位置づけた。しかし、この事件の本質は本当にライシテの危機だったのだろうか。
本来、ライシテは共和主義者とカトリック教徒との和解のために成立した原則であり、宗教そのものを否定するものではなかった。ところが、近年のイスラム系移民の増加とそれに伴う文化的摩擦によって、ライシテの意味は変質しつつある。今やそれは「宗教との妥協」ではなく、「宗教の排除」を意味するものへと傾いている。
風刺週刊誌『シャルリ・エブド』は、過激かつ侮辱的な表現でイスラム教や預言者ムハンマドを繰り返し風刺していた。表現の自由という名のもとに、他者の宗教的尊厳を傷つける権利が主張されたのである。果たして、ライシテはそのような冒涜的表現までも無条件に正当化する原則なのだろうか。
なぜライシテは変質したのか
このライシテの変化の背後には、フランス社会における深層の価値観の変動がある。エマニュエル・トッド氏は、人口社会学の視点から、この変化を読み解こうとしている。
分裂するフランス:地域による価値観の対立
トッド氏は、フランス国内に二つの地域的文化圏が存在すると指摘する。
一つは、パリ盆地や南仏プロヴァンス、地中海沿岸部を含む地域であり、平等主義的な家族構造を持ち、脱宗教的で、共和政的自由と親和性が高い。
もう一方は、アルザス、ノルマンディー、ブルターニュなどの周辺地域で、伝統的なカトリック文化を色濃く残す一方、家族構造は権威主義的である。これらの地域では1960年代以降、急速な脱宗教化が進み、信仰を持たないがカトリック文化の影響を受け続ける人々、すなわち「ゾンビ・カトリシズム」が広がっている。
ゾンビ・カトリシズム層の政治的影響
このゾンビ・カトリシズム層は、かつてはキリスト教右派に属していたが、1965年から1990年代にかけて急速に社会党支持へと転じた。そして1992年のマーストリヒト条約の国民投票では、ヨーロッパ統合とユーロ導入を積極的に支持した主要な層となった。
この層の特徴としては、権威主義的な社会主義志向、地方分権志向、ヨーロッパ主義(反共和主義的傾向)、そしてユーロへの支持といった政治的傾向が見られる。トッド氏は、2015年の「私はシャルリ」デモの主導的役割を果たしたのも、この地域の人々だったと指摘している。
ゾンビ・カトリシズムが抱える不安
シャルリ・エブド襲撃事件に際し、フランスで「自由とライシテを守る戦い」が叫ばれた。その中心にいたのは、共和政の中枢から外れ、現在では周縁的地位にある地域の人々だった。しかし、彼らが掲げた「ライシテ」は、宗教と世俗の妥協を目指すものではなく、むしろ表現の自由を「他者の信仰を冒涜する権利」と捉える、攻撃的な形へと変質していた。
トッド氏は、このようなライシテの変容の背景に、イスラム恐怖症(イスラモフォビア)と反ユダヤ主義の再興という深刻な社会病理を見て取る。ライシテは今や、イスラム教に対する偏見を隠蔽するための「正当な装い」となりつつあるのだ。
宗教的空白が生んだ恐怖と敵意
このようなイスラム恐怖症の蔓延には、1960年代以降に進行したカトリック地域での脱宗教化=宗教的空白の拡大が深く関係している。宗教的支柱を失ったこの地域では、その空白を埋めるかのように、EUやユーロといった「世俗的な普遍価値」への支持が一時的に高まった。
しかし、その期待とは裏腹に、ユーロ導入は経済的困難と格差の拡大をもたらした。通貨政策の主権を失ったフランスは、財政引き締めによる長期停滞と高失業率に苦しみ、その打撃は特に周辺地域の中間層・若年層に重くのしかかった。この不満と疎外感が、イスラム系移民への敵意に転化していったとトッド氏は分析する。
排外感情の根底にあるもの
著者の結論は明快かつ悲観的である。宗教的空白と経済的格差の拡大は、外国人嫌悪を引き起こす。シャルリ襲撃事件後に盛り上がりを見せた「私はシャルリ」のデモは、建前としてはライシテの擁護を掲げていたが、実態はイスラムへの恐怖と敵意の集団的な発露であった可能性がある。
共和政を守るためのライシテと同化主義
「冒涜する権利」を守っても、イスラム系移民との軋轢は深まるばかりだ。むしろ、共和政の理念そのものを脅かしかねない。真にフランスに必要だったのは、対立ではなく融和であったはずだ。
トッド氏は、あくまでも共和主義者かつ同化主義者として、ライシテを重視しつつも、宗教的寛容と移民の受け入れを主張する。ライシテは、公共空間での宗教的表示を制限するものであるが、それは宗教そのものを否定することとは異なる。相手の信仰を不必要に冒涜することは、ライシテの名においても正当化されるべきではない。
同化の可能性と責任の所在
人口統計的に見れば、移民は世代を重ねるにつれて地域社会に自然と同化していく。特に第三世代では、混血や文化的融合が進み、彼らは次第に「フランス人」として社会に溶け込んでいく。このプロセスにおいて重要なのは、同化に失敗するのは移民ではなく、社会の側であるという著者の指摘である。
共和政が進むべき道は明白だ。宗教と政体の間に妥協を築きながら、ライシテを再確認し、移民の社会的包摂を後押しすることが求められている。
シャルリとは誰か?
シャルリ襲撃事件に端を発した「Je suis Charlie」の運動を通じて、著者は、現代社会が抱える宗教的空白、経済的分断、排外主義の連鎖という普遍的問題を浮き彫りにした。
このような問題は、決してフランスに特有なものではない。むしろ、どの社会にも見られる構造的現象だ。経済の停滞、社会的アイデンティティの喪失、そしてスケープゴート探し——これらは、世界中で繰り返される人間社会の宿命的なパターンである。
シャルリ——それは、どの社会にも存在しうる「他者」への不安と攻撃性の象徴であり、時に自由を語りながら、実は恐怖と排除の感情を包み隠す仮面でもある。
本書は、シャルリ襲撃事件というフランスの一地域的な問題を考察したものではなく、人間社会の普遍的な特質に光を当てた研究として読まれるべきだろう。
『シャルリとは誰か?』——それは、どの社会にも存在することを忘れてはならない。
エマニュエル・トッド『シャルリとは誰か? – 人種差別と没落する西欧』(2016)
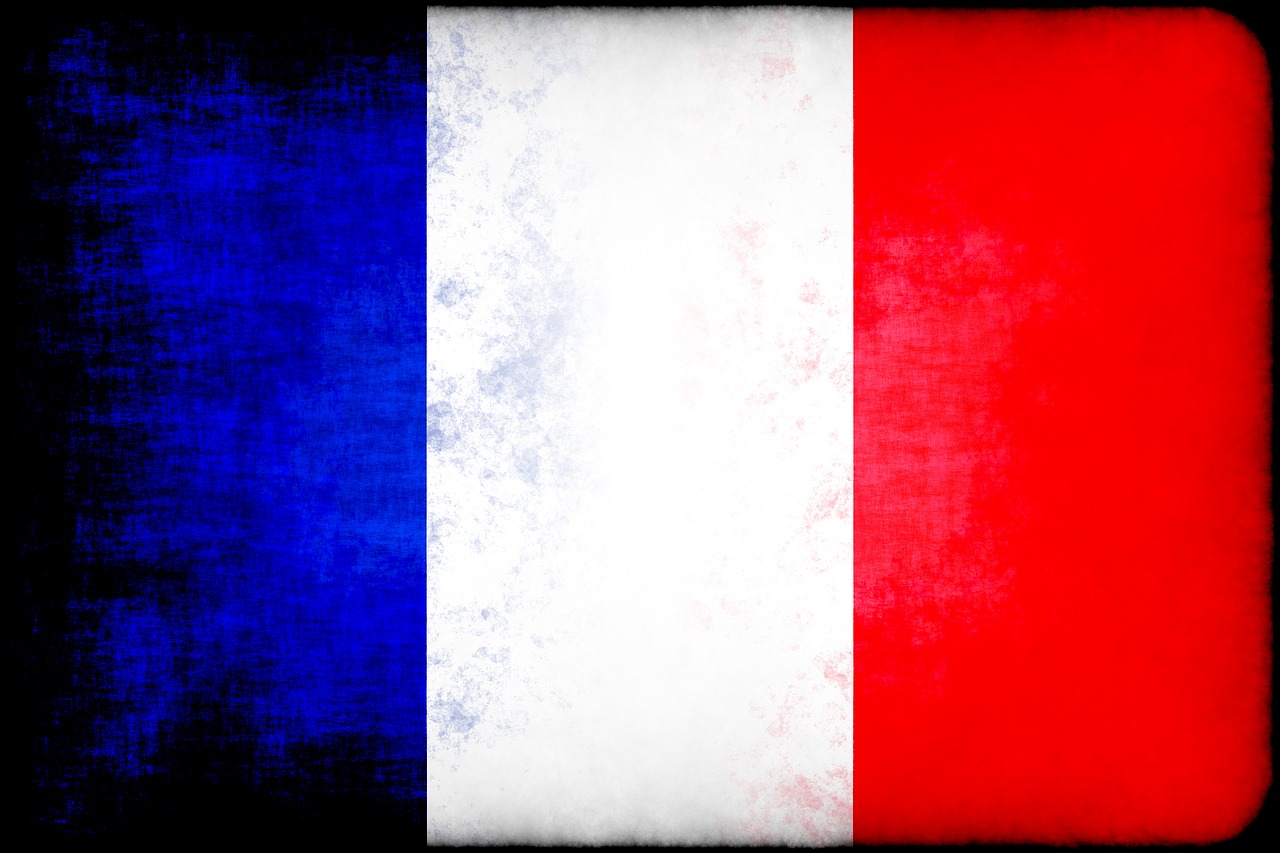


コメント