 暮らし・生活
暮らし・生活 廃品回収車の騒音は誰の責任か──利用者が問われる公共意識
騒音公害と公共意識──利用者にも問われる責任 公共の生活環境は、制度や規制だけでなく、地域住民一人ひとりの意識と行動によって維持されている。 だが、拡声機を用いた廃品回収車などによる騒音問題は、都市部を中心に何年も放置され続けている。長年に...
 暮らし・生活
暮らし・生活  暮らし・生活
暮らし・生活  暮らし・生活
暮らし・生活  独立・起業
独立・起業  投資・市況
投資・市況  音楽・映画
音楽・映画  投資・市況
投資・市況  科学・技術
科学・技術  科学・技術
科学・技術  運動・健康
運動・健康 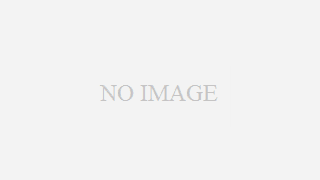 科学・技術
科学・技術  企業・経営
企業・経営