ジャレド・ダイアモンド『銃・病原菌・鉄』(1997)
壮大な人類史への試み
本書『銃・病原菌・鉄』の原著は1997年に刊行。現在では20年以上前の著作となる。邦訳は文庫版で上下巻に分かれている。
さすがに刊行から時間が経過しており、現在の人類学や考古学の研究成果と照らし合わせると、すでに否定されている説や古さを感じる記述も散見される。たとえば、著者はネアンデルタール人について、クロマニョン人(現生人類)によって滅ぼされたという立場に近い見解を示しているが、近年の研究では、両者の間に交配や共存があったとする説が有力である。こうした点は、本書を読む際に頭に入れておくべきだろう。
それでもなお、本書が人類学、考古学、植物学、動物学、疫学といった多岐にわたる分野を横断し、「人類史」という俯瞰的な視点で歴史の大きな流れを描き出したことは特筆に値する。各論については、専門家から多くの批判が寄せられているが、ひとつの視座としての価値は高く、今なお一読に値する。気になった箇所があれば、最新の研究成果をネットや文献で補完しながら読むと、より深く理解できるだろう。
人種的決定論から環境決定論へ
本書はまず、「なぜ現代の世界において、文明や富の分布に大きな差が生まれたのか」という問題提起から始まる。ダイアモンドはこの差を、人種や文化、宗教といった要因ではなく、主に地理的・環境的な要因によって説明できると主張し、それを複数の学問領域の成果を援用しながら検証していく。
たとえば、人類が初めて狩猟採集から農耕社会へと移行したのは、メソポタミア地方、特に「肥沃な三日月地帯」と呼ばれる地域であった。これは偶然にも、農耕に適した野生植物や家畜化可能な動物種がこの地域に集中していたためである。こうした野生種は、人間による選別と管理を通じて、意図的あるいは無意識のうちに栽培化・家畜化されていった。
一度、農耕や牧畜が始まると、それらの技術や生物種を継承・伝播するほうが、新たに適した種を発見し改良するよりも圧倒的に容易である。そのため、農耕・牧畜の伝播速度が、地域ごとの発展速度に大きく影響したとされる。
また、ユーラシア大陸は東西方向に長く、緯度による気候の変化が少ないため、この地域では農耕技術が比較的早く広まった。一方、南北に長く気候帯が多様なアメリカ大陸や、乾燥地帯の多いアフリカ大陸では、その伝播が遅れた。この地理的・環境的要因が、各地の文明発展の差異を生み出す大きな要因となった。
さらに、農耕社会への移行は、食糧の増産を可能にし、人口増加と定住化、そして社会の複雑化をもたらす。その結果、家畜との接触を通じて発生した感染症が、密集した社会に蔓延するようになる。つまり、病原菌への耐性を獲得するプロセスもまた、農耕化の早さに比例する。ヨーロッパ人が15世紀にアメリカ大陸へ到達した際、現地の先住民が免疫を持たなかったために、多くの犠牲者を出したのはその一例である。
このように、地理的・生態的な条件が、社会の発展や衝突の歴史に決定的な影響を与えたというのが、本書の根幹をなす主張である。
地域ごとの検証と個別事例
下巻は、まず文字の発明、技術の受容、社会の集権化を概説した後に、上巻で示した仮説を敷衍して個別の地域への検証を行っている。
上巻のような壮大な仮説と比べると、やや地味に感じられる部分もあるが、細部には興味深い指摘やユニークな視点が盛り込まれており、読み進めて飽きることはない。
印象的だった点をいくつか挙げると──
- 初期の文字は、メソポタミア、エジプト、中国、メキシコといった農耕文明の発祥地で誕生している。当初の文字は用途が限定されており、表現力も乏しかった。主に支配階層による統治手段として利用されていた。
- 技術の受容性は、同じ地域であっても時代によって異なる。社会の文化的・政治的状況が、技術導入の可否を左右する。
- オーストラリア大陸では、アボリジニが農耕に不向きな環境(乾燥した砂漠地帯)に適応し、狩猟採集生活を続けたのに対し、ニューギニアではより農耕に適した環境が存在した。この地理的要因が両者の社会発展に差を生んだ。
- 中国では、地形的な障壁が少なく平坦な土地が多かったため、早期に広域的な政治統一が進んだが、同時にそれが過度な中央集権を生み、政治的自由を抑制し、内部の技術競争を妨げた面もある。
このように見ていくと、タイトルにある「銃・病原菌・鉄」は、人類史の決定的要因というよりは、地理的・環境的条件が生み出した多様な結果の象徴と捉えるべきだろう。むしろ、「銃」「病原菌」「鉄」という各テーマを独立した主題として深掘りした別の著作があっても面白いと思わせる構成である。
まとめ
『銃・病原菌・鉄』は、あくまでも壮大な仮説に基づく一つの「歴史観」を提示するものであり、全ての記述を鵜呑みにすべきではない。しかし、文明の発展における「偶然」と「地理的必然性」を示したという意味で、知的興奮を与えてくれる名著である。現在の知見と照らし合わせながら読むことで、より深い理解と批判的思考を養える一冊だ。
ジャレド・ダイアモンド
『銃・病原菌・鉄(上巻)』(2013)
『銃・病原菌・鉄(下巻)』(2013)
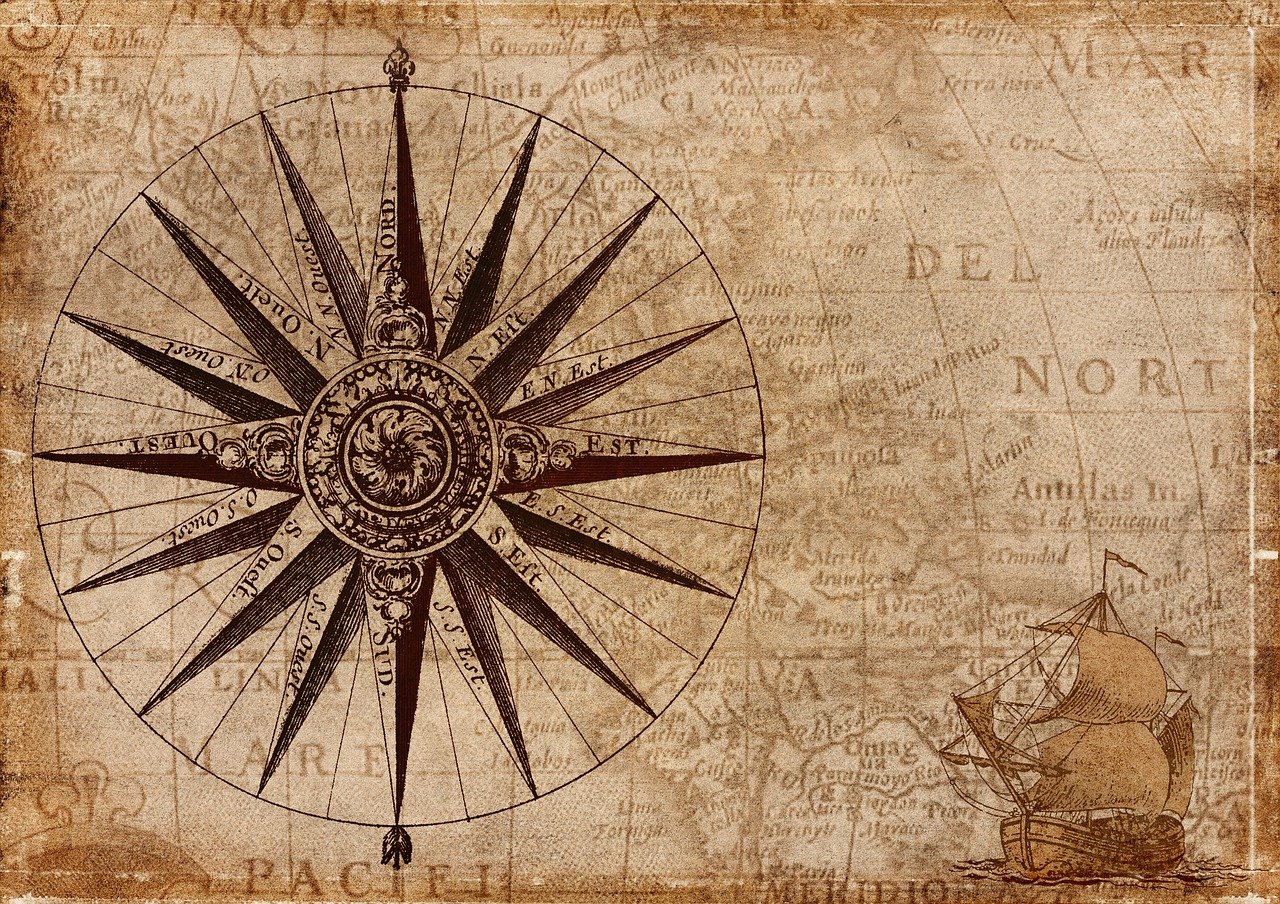

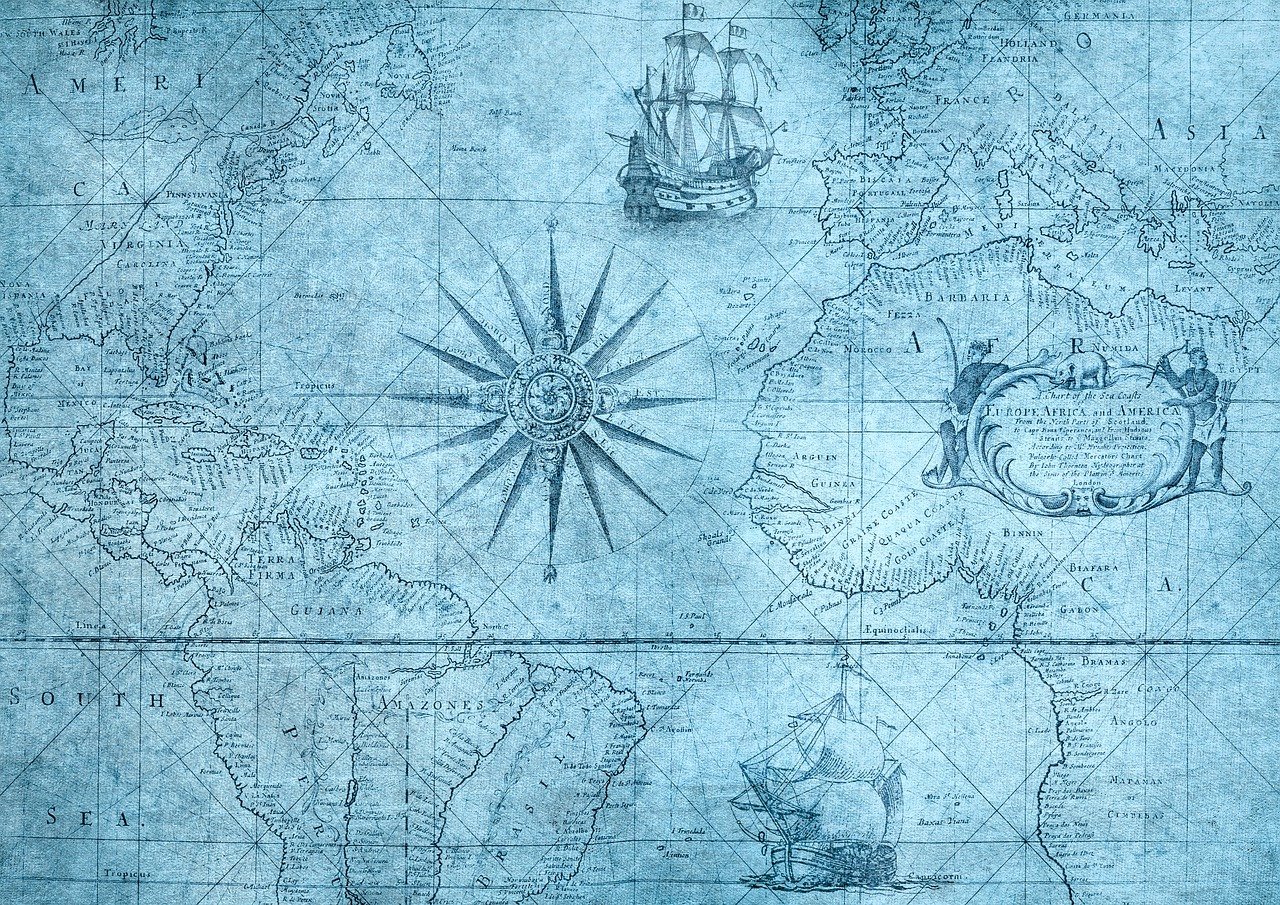
コメント