中国は経済的軍事的な脅威である – CIA長官発言
2021年1月、アメリカの政権はトランプ共和党政権からバイデン民主党政権へと移行した。この政権交代は一見すると外交政策の大きな転換点のように見えるが、アメリカの国家戦略の根幹においては、むしろ一貫性が際立っている。
バイデン政権下でCIA長官に指名されたウィリアム・バーンズ元国務副長官は、2021年2月24日の上院公聴会で、中国を「独裁的な敵対国」と明言し、今後の国家安全保障の鍵は「中国への対抗」であると述べた。また、「これは長期的な挑戦になる」とも述べ、同盟国との緊密な連携の必要性を強調した。
CIAは情報機関であると同時に、アメリカの国家戦略の形成に深く関与する政策機関でもある。つまり、バーンズ氏の発言は今後のアメリカの対中戦略を示すシグナルであり、政権が変わってもアメリカの基本戦略が継続していることを示している。
アメリカのCIA=中央情報局の長官に指名されたバーンズ元国務副長官は24日、上院の公聴会で、中国は「独裁的な敵対国」だと指摘し、「中国に対抗することが今後の国家安全保障の鍵となる」と述べました。
テレ東BIZ(2021年2月25日)
その上で、「長期間にわたる挑戦になるとはっきり認識することが極めて重要だ」として、世界各地の同盟国などと緊密に連携して対応する必要があると説明しました。
CIAによる対日戦略「JAPAN2000」
中国に対する強硬姿勢は、アメリカが過去に日本を「経済的脅威」と見なして展開してきた戦略とも重なる。
1980年代、日米間の貿易・経常収支の不均衡が深刻化するなか、アメリカは国家戦略として日本に圧力をかけ始めた。
1990年には、当時のベイカー国務長官が「冷戦の戦勝国は日本だった。冷戦後も戦勝国にしてはならない」と発言。
翌91年には、CIAが「JAPAN2000」と呼ばれる戦略文書を策定する。制作には、ロチェスター工科大学などの著名な学者たちが関わった。これは、アメリカが日本からの経済的な脅威にさらされているという認識の下、2000年までに日本の経済的影響力を削ぐことを目的とした計画書だった。
その後の日本の経済的凋落は、まさにアメリカの思惑通りに展開した。
規制緩和、構造改革、金融ビッグバン、郵政民営化、労働市場自由化、等々、「グローバリズム」と「市場原理」の名の下に、90年代を通じて矢継ぎ早に新政策が日本へと導入されていったが、それらの政策はすべてアメリカの意向の下、アメリカ政府から発行される「年次改革要望書」によって実施されていたことが今では分かっている。
アメリカは80年代からすでに日本を経済的な脅威と見做して国家戦略を描いていた。CIAの「JAPAN2000」は、10年先という超長期を見据えた戦略であるが、それでさえ、さらに長期的なアメリカの国家戦略の流れの中の一つという位置付けだろう。
プラザ合意(1985)、前川リポート(1986)、日米構造協議(1989)、年次改革要望書(2001~9)と一貫して、アメリカは日本の経済構造、社会構造の変革を要求してきた。90年代以降の自民党による経済政策が、すべてアメリカの意向を汲んだ米国家戦略に従って行われていたことは間違いない。
アメリカは、国家戦略として一つの政策目標を定めたら、その目標に向け、あらゆる手段を取り、可能な限りの資源を投入する。そして、超長期間にわたり、多方面での諸政策を整合的に、かつ、粘り強く着実に実施していく。その間の政権交代も、野党与党、共和党、民主党も関係ない。政策立案における合理性、超党派的な組織性、整合的な一貫性———これがアメリカの国家としての強さなのだ。
アメリカに追随するだけだった日本
では、一方の日本はどうだったのか。
結論から言えば、日本には国家戦略と呼べるような構想が存在していなかった。アメリカの要求に唯々諾々と従い、自らの主体的な戦略を持つことなく、受け身の政策運営に終始してきた。そもそも、長期的な国家像を描き、戦略を立案・遂行する能力を持った政治家や官僚が、当時も、そして現在も、決定的に欠けている。
米国に対抗しようにも、与野党間で基本政策はおろか、国家像すら共有されていない。この構造的な欠陥は、冷戦終結後の30年を経ても、ほとんど改善されていない。
「失われた30年」の意味
1980年代の日米貿易摩擦以降、日本は経済的にアメリカに敗退し続けてきた。中曽根政権、橋本政権はアメリカの要望に従う形で政策を実行し、小泉・安倍政権に至っては、対抗する姿勢すら見せず、むしろ積極的に追従する方向へと舵を切った。
90年代の日本は「失われた10年」と呼ばれたが、それはすでに「失われた30年」となり、さらに長期化する可能性すらある。この間に推進された新自由主義政策によって、産業の空洞化が進み、国際競争力は著しく低下した。労働市場の自由化により中間層は没落し、格差社会が定着した。
自民党は事実上、アメリカ主導の改革に追従してきた政党であり、野党もまた政権を担う覚悟と実力を欠いている。こうした政治の不在が、日本の衰退を固定化させてきた。将来「失われた50年」と呼ばれる時代が到来しても、不思議ではない。
日本の経済的衰退は、アメリカの周到な国家戦略の結果だと言える。軍事外交面で日米は友好関係にあるが、日米貿易摩擦が深刻化して以降は、アメリカは間違いなく日本を経済上の仮想敵国と見做して対応してきた。冷戦後、アメリカが経済上では敵となったことに多くの日本人は気づいていなかった。それが今の経済的凋落と経済格差の拡大へとつながっていった。まさに戦略なき国家の悲劇と言えるだろう。
今後の対中戦略と日本の選択
日本に代わって台頭したのが中国である。アメリカが中国を次なる経済的・地政学的脅威と見なすようになったのは、2010年頃からと見られる。米中貿易戦争はトランプ政権下で表面化したが、その前から戦略的な準備は進められていたはずだ。
政権がバイデンに代わった後も、アメリカの対中戦略に大きな転換はなく、むしろより強硬な姿勢を見せている。ここに、アメリカの戦略の「一貫性」——党派を超えて国家目標を継続的に追求する姿勢が現れている。
では、そのとき日本はどうあるべきか。
日米貿易摩擦の時代、アメリカは日本を経済的な脅威、時に仮想敵国として扱った。だが、現在の米中対立では、中国は経済的脅威であると同時に、軍事的脅威ともなっている。中国共産党政権の体制的性質を考えれば、アメリカが中国を「包括的な敵」として捉えるのは自然な流れだろう。
こうした中で日本は、アメリカと協調して国際的な対中戦略を構築していく必要がある。ただし、それはアメリカの指示をそのまま受け入れる「従属的協力」ではなく、日本独自の国家戦略に基づく主体的判断によってなされるべきである。
繰り返してはならないのは、過去のように「戦略なきまま、外圧に追随するだけの国家」になることだ。アメリカの戦略から学ぶべきは、対抗ではなく、その冷徹なまでの合理性と長期的な一貫性である。
いま、日本に求められているのは、対中戦略の中での「主体性」だ。そしてそれは、戦略を持つ国家への第一歩となる。
二度と「戦略なき国家の悲劇」を繰り返してはならない。


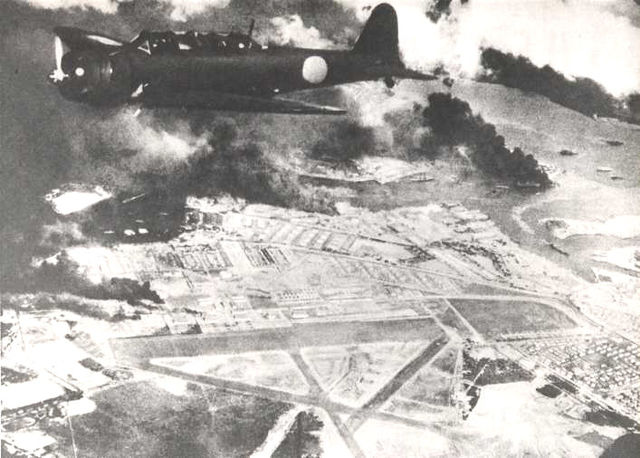
コメント