人手不足による倒産は「経済的に正しい」
近年、日本では少子高齢化が急速に進行し、多くの産業で深刻な人手不足が顕在化している。その結果、労働力を確保できずに事業継続が困難となり、「人手不足倒産」が増加している。これを一見すると経済の危機のように受け止めがちだが、実は経済原理の観点からみれば、人手不足による倒産は「経済的に正しい」現象だといえる。
需要不足ではなく「経営の非合理」が原因
倒産には大きく二つの要因がある。一つは需要不足である。消費や投資が冷え込み、売上が確保できないために企業が倒れる。この場合、政府が公共投資や金融政策を通じて有効需要を創出し、景気を刺激することが正当化される。
しかし、人手不足による倒産は、このケースに当てはまらない。人手不足とは、需要が旺盛なことを示していて、むしろ供給が追いついていない状況だ。つまり、問題は経営側が人材確保のための賃金引き上げや労働環境改善といった合理化を進められなかったことにある。
外国人労働者の受け入れは「延命措置」にすぎない
人手不足を解消するために、外国人労働者を積極的に受け入れようという議論は依然として根強い。しかし、それは非合理な経営を温存する危険をはらんでいる。労働条件の改善や生産性向上といった本質的な改革を怠った企業にとっては、単なる延命策に終わる可能性が高い。
特に、単純労働を低賃金の外国人労働者に依存することは深刻な問題を引き起こす。第一に、それは賃金水準に下方圧力を与え、労働者全体の待遇改善を阻害する。第二に、労働市場が本来持つ「労働環境を改善しなければ人材を確保できない」という健全な調整メカニズムを歪めてしまう。
結果として、日本経済が少子高齢化の中で避けて通れないはずの構造転換──すなわち、生産性の向上や賃金の適正化──が進まず、経済全体の持続的な成長すら妨げられる危険がある。
政府は介入すべきでない
人手不足倒産は、需要不足倒産とは本質的に異なる。需要が旺盛である以上、景気刺激策は不要であり、政府が積極的に介入する理由はない。むしろ市場原理に委ねることが重要だろう。
市場はやがてバランスを回復する。需要が旺盛であれば、それに応えようとして、適正な賃金を提示して人材を確保し、そのコストを価格に適正に転嫁することのできる企業が必ず現れる。つまり、市場原理が適切に働く場面では、人材を適正に確保できる企業が、遅かれ早かれ自然と現れるということだ。逆に、非合理的な経営に固執し、労働者を確保できない企業は退出する。これは一見厳しい淘汰のように見えるが、長期的には経済全体の効率性を高める健全なプロセスである。
経済の「正しい淘汰」としての人手不足倒産
人手不足による倒産は、社会にとって必ずしも不幸な出来事ではない。それは、労働市場のひずみを正し、生産性の低い企業を退出させる「正しい淘汰」の現れである。これを外国人労働力の大量受け入れによって抑え込むのは、経済の新陳代謝を阻害することに他ならない。
少子高齢化が不可避の日本経済においては、非合理な経営を続ける企業の安易な延命ではなく、賃金の適正化や労働環境の改善を通じた合理化こそが必要とされる。
外国人労働力依存がもたらす「社会の分断」
仮に人手不足を海外からの労働力によって補おうとすれば、別の深刻な問題が生じる。それは社会の分断である。
外国人労働者が相対的に安い労働力として導入されれば、当然のことながら賃金水準には下方圧力がかかる。企業は低コストで労働力を確保できるため、賃金の引き上げや労働環境の改善を後回しにする。結果として、その業種は「低賃金・劣悪な環境」のイメージが固定化され、日本人が積極的に就職しようとはしなくなる。
すると、その業種はますます外国人労働者に依存せざるを得なくなり、悪循環が生じる。最終的には「外国人しか就かない職種」が社会に定着してしまう危険がある。これは単なる経済問題ではない。職業が日本人と外国人とで分断されることは、やがて経済格差を生み出し、さらには人種的な格差や偏見を助長することになる。
分断がもたらす社会不安
こうした社会の二層化は、やがて社会全体の不安定化を招く。欧米諸国の事例がその典型である。大量の移民労働者を受け入れた結果、一部の職業が移民に固定化され、低賃金・低待遇の「移民職種」として認識されるようになった。これは社会の不満や差別意識を生み、ポピュリズムや排外主義の台頭を後押ししてきた。
日本が同じ道をたどるのであれば、短期的には人手不足を補えても、長期的には深刻な社会不安を抱えることになる。人手不足倒産を「救う」ために外国人労働者に頼ることは、経済合理性を損なうだけでなく、社会の分断という重大なリスクを将来世代に押し付ける選択なのである。
日本が取るべき道 ― 賃金引き上げと生産性向上への転換
人手不足倒産を外国人労働力によって解消することは、短期的な延命措置にはなり得るが、長期的には経済の非合理と社会分断を深める危険な選択である。では、日本はどうすべきなのか。
第一に必要なのは、賃金の引き上げである。労働市場における人手不足は、労働の価値が高まっていることの表れだ。本来であれば、企業は労働者を確保するために賃金を上げ、働きやすい環境を整えるべきである。これは市場経済の自然な調整メカニズムであり、むしろ健全なプロセスだ。
第二に求められるのは、労働生産性の向上である。人手が限られる以上、既存の労働力でより大きな成果を上げるための仕組みが不可欠だ。IT投資やデジタル化、効率的な業務プロセスの導入によって、限られた人材でも高い付加価値を生み出せるようにしなければならない。
第三に不可欠なのが、自動化や省力化への投資である。特に製造業やサービス業など人手依存度の高い分野では、ロボットやAIを活用したオートメーションが人手不足解消の鍵を握る。これらの技術革新は初期投資を要するが、長期的には生産性を飛躍的に高め、日本経済の競争力を維持する基盤となる。
つまり、日本が進むべき方向は、外国人労働力への過度な依存ではなく、人材の価値を正当に評価し、賃金と労働環境を改善しつつ、技術と生産性の向上によって少子高齢化時代を乗り越えることだろう。人手不足倒産は一見すると痛みを伴うが、それは日本経済が非合理を改め、次の段階へと進化するための通過点にほかならない。
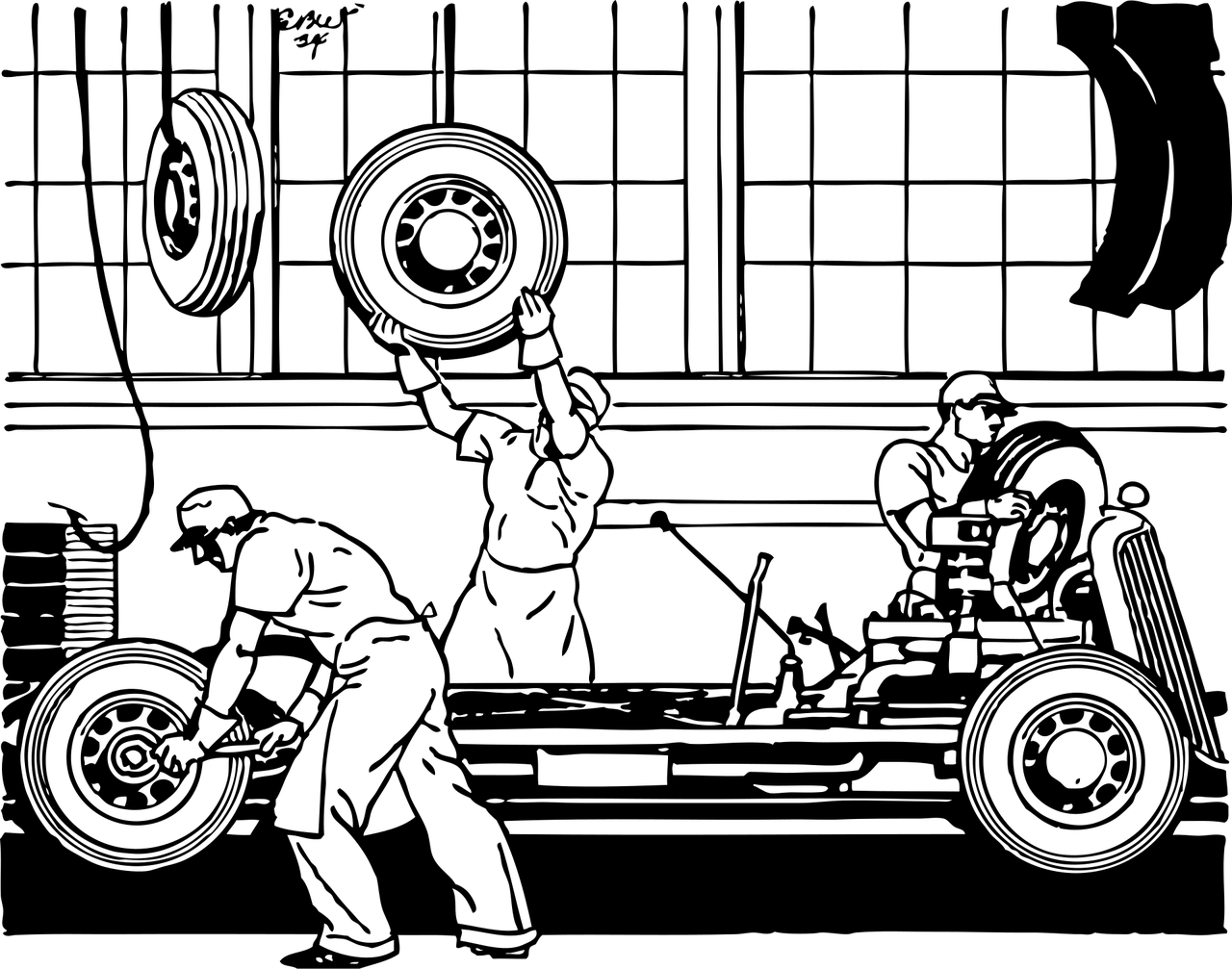


コメント