「ついていけないけど、支援の対象にならない」子どもたちの現実
「どうしても授業についていけないけど、特別な支援を受けるほどではない」——そんな“はざま”にいる子どもたちがいます。その中核にあるのが「境界知能」という概念です。これは、軽度知的障害とも深く関係しながらも、制度や周囲の認識の狭間で、しばしば“見逃される存在”となっています。
境界知能とは何か?
境界知能とは、知能指数(IQ)が70以上85未満の子どもたちを指します。これは、IQの平均値100から1標準偏差(15)を下回った範囲であり、「平均」とされるIQ85〜115にはわずかに届かない層です。
一般的にIQ70未満は知的障害と判断され、特別支援教育の対象になります。しかし、境界知能の子どもたちは支援の対象とされることが少なく、「普通学級」での生活を求めらます。
結果として、学習についていけず、努力不足や怠けと誤解される場合が少なくありません。
なぜ支援が必要なのか?:認知機能という「学習の土台」
学習がうまくいかない背景には、知能の問題ではなく、「記憶力」「注意力」「言語理解力」「知覚」「推論・判断力」などの認知機能の弱さが関係していることがあります。これはWISCなどの知能検査だけでは把握しにくく、より実践的な視点が求められます。
子供を対象とした知能検査
現在、日本でも広く活用されている子どもを対象とした知能検査には、WISC-V(ウィスク・ファイブ)があります。この検査は、6歳から16歳11か月までを対象とし、全体的な知能指数(FSIQ)に加えて、5つの主要な指標(インデックス)を算出することで、知能の構成要素をより詳細に評価できるようになっています。
WISC-Vの構成
・全検査IQ(FSIQ: Full Scale Intelligence Quotient)
個人の全体的な知能発達の水準を示す指標であり、知的能力の総合得点にあたる。10種類の主要な下位検査のうち7つ(類似、単語、積木模様、行列推理、バランス、数唱、符号)から算出される。
各指標とその内容
① 言語理解指標(VCI: Verbal Comprehension Index)
言葉を用いた理解、推理、思考の力を評価する指標である。語彙力や概念形成力、言語的な情報の意味を捉える力などが測定される。
・主要下位検査項目:類似、単語
② 視空間指標(VSI: Visual Spatial Index)
目で見た情報をもとに空間的な構成や関係性を理解・処理する能力を測定する。視覚的な問題を解く力、手と目の協調動作も含まれる。
・主要下位検査項目:積木模様、パズル
③ 流動性推理指標(FRI: Fluid Reasoning Index)
言語に頼らず、視覚的なパターンや関係性をもとに推論を行う力を測る。新しい問題に対して柔軟に思考を展開し、規則性やルールを見出す能力が問われる。
・主要下位検査項目:行列推理、バランス
④ ワーキングメモリ指標(WMI: Working Memory Index)
耳で聞いた情報や視覚情報を短時間保持しながら、同時に処理する能力を測定する。情報の一時的な記憶と操作を行う力であり、学習や注意力と深く関係している。
・主要下位検査項目:数唱、絵のスパン
⑤ 処理速度指標(PSI: Processing Speed Index)
視覚的な情報をどれだけ正確かつ素早く処理できるかを測定する。注意力や視覚探索の能力、作業効率などもこの指標に影響する。
・主要下位検査項目:符号、記号探し
なお、これらの5つの指標に加えて、必要に応じて実施する補助指標(追加検査項目)も存在します。補助指標は、特定の認知機能に偏りがある場合や、より詳細な診断が求められる場合に活用されています。
WISC-Vは、単にIQを算出するだけでなく、子どもの強みや課題を多面的にとらえることができる評価ツールです。その結果は、特別な支援を要する子どもへの教育的対応を検討する際の基礎資料として重要な役割を果たしています。
認知機能の階層構造について
認知機能には階層的な構造があるとされており、これは「下位の認知機能が上位の機能の土台となり、上位機能に影響を及ぼしている」という考え方に基づいています。つまり、最も基礎的な覚醒や注意の機能が十分に働かなければ、その上に位置する論理的思考力や自己同一性といった高次の認知機能も適切に発揮されにくくなるということです。
この階層構造の視点から見ると、知的障害が認められない場合であっても、一部の認知機能、特に高次の機能である論理的思考力や実行機能に困難を抱えるケースが存在します。こうした特徴は、いわゆる境界知能と呼ばれる子どもや若者によく見られます。
以下は、認知機能の階層構造を下位から上位へと順に示したものです。この構造を理解することは、適切な支援やリハビリテーションの介入を考えるうえで非常に重要です。
認知機能の階層構造(上位から下位)
- 自己同一性(Ego Identity)
── 自分は何者であるかという自己理解や、自尊心の形成に関わります。 - 受容(Acceptance)
── 自分の課題や現実を受け入れ、適応しようとする心理的な態度です。 - 論理的思考力(Reasoning)・実行機能(Executive Functions)
── 問題解決、計画立案、判断、柔軟な思考など、複雑な認知操作を含みます。 - 記憶(Memory)
── 短期記憶や長期記憶など、情報を保持し活用する力です。 - コミュニケーションと情報処理(Communication and Information Processing)
── 言語や視覚・聴覚などを通じて情報を理解・処理する能力です。 - 注意と集中(Attention and Concentration)
── 外的刺激や課題に対して注意を向け、それを維持する力です。 - 制御(Control)・発動性(Initiation)
── 行動を開始したり、行動を制御したりする能力で、実行の前提となります。 - 覚醒(Arousal)・警戒態勢(Alertness)・心的エネルギー(Energy to Engage)
── 意識レベルや注意喚起の基盤となる、最も基礎的な機能です。
このように、認知機能は単独で存在するのではなく、相互に影響しあいながら階層的に働いています。特定の機能に困難がある場合には、その下位機能の支援や補強が上位機能の改善にもつながる可能性があります。そのため、支援や介入を行う際には、この階層構造を踏まえて、基礎から順にアプローチしていくことが重要です。
「9歳の壁」と境界知能の子どもたち
発達心理学では、小学校中学年(おおよそ9歳前後)に、「抽象的思考」や「他者の立場に立つ力」が飛躍的に伸びる転機があるとされ、これを「9歳の壁」と呼びます。
しかし、境界知能の子どもたちは、発達年齢がおよそ7〜8割程度の進度であることが多く、この壁にぶつかるのが12歳ごろになる場合もあります。そのため、中学生になってから急に学習や人間関係がうまくいかなくなるといった現象も起こりやすくなります。
支援のアプローチとしてのコグトレ:具体的実践と可能性
WISCなどの知能検査は、子どもの知的水準を把握する有効な手段です。しかし、具体的な弱点や課題を明確にするには不十分な場合もあります。こうした認知機能の育成を目的とした支援方法が、コグトレ(Cognitive Function Training)です。WISCの結果をもとに、さらにコグトレの課題を使って認知機能を評価・強化するという方法が効果的です。
また、脳には「可塑性」があります。すなわち、適切な刺激を与えることで、子どもの脳は発達・変化し続けるのです。早期からの働きかけによって、子どもの持っている可能性を大きく広げることができるのです。
コグトレで育てる5つの認知機能
コグトレは、子どもの苦手な認知機能に働きかけ、「学ぶ力」や「人と関わる力」を底上げするためのトレーニングです。主に以下の5つの力を育てます。
覚える力(記憶・ワーキングメモリ)
視覚・聴覚を通して入った情報を一時的に保持し、操作する「作業記憶」を鍛える課題です。これにより、授業中の説明を覚え、理解しながら行動する力が向上します。
数える力(数概念・処理速度)
数字や記号を素早く数える、計算するなどの課題を通じて、注意力・集中力・処理速度を高めます。基礎的な数の概念が育っていない子にとっても有効です。
写す力(視覚認知)
図形の模写などを通して、視覚情報の処理や空間認識、形の把握力を養います。文字の書き写しや図形問題にも関係する力です。
見つける力(視覚的な注意・識別)
似たものや異なるものを識別する力を育て、情報を分類・整理する力を高めます。混乱しやすい板書や教材の読み取りにも有効です。
想像する力(推論・論理的思考)
情報から見えない背景を想像する力や、計画・実行する「実行機能」をトレーニングします。この力は、算数の文章題、人間関係、社会的な場面の理解に直結します。
見過ごされがちな子どもたちに光を
境界知能や軽度知的障害の子どもたちは、見た目には「普通」に見えることから、支援が後回しにされやすい存在です。しかし、「気づかれない苦しさ」こそが、最も深刻な困難を引き起こします。
認知機能という視点に立ち返り、学びの土台を丁寧に育てる支援こそが、彼らにとっての本当の“学ぶ権利”を保障することにつながります。
コグトレのようなアプローチを通じて、「できない」から「できる」に、「わからない」から「わかる」に変わる体験を一つひとつ積み重ねていく——その積み重ねが、子どもたちの未来を確かに支えていくのです。
参考
宮口幸治『境界知能の子どもたち 「IQ70以上85未満」の生きづらさ』(2023)

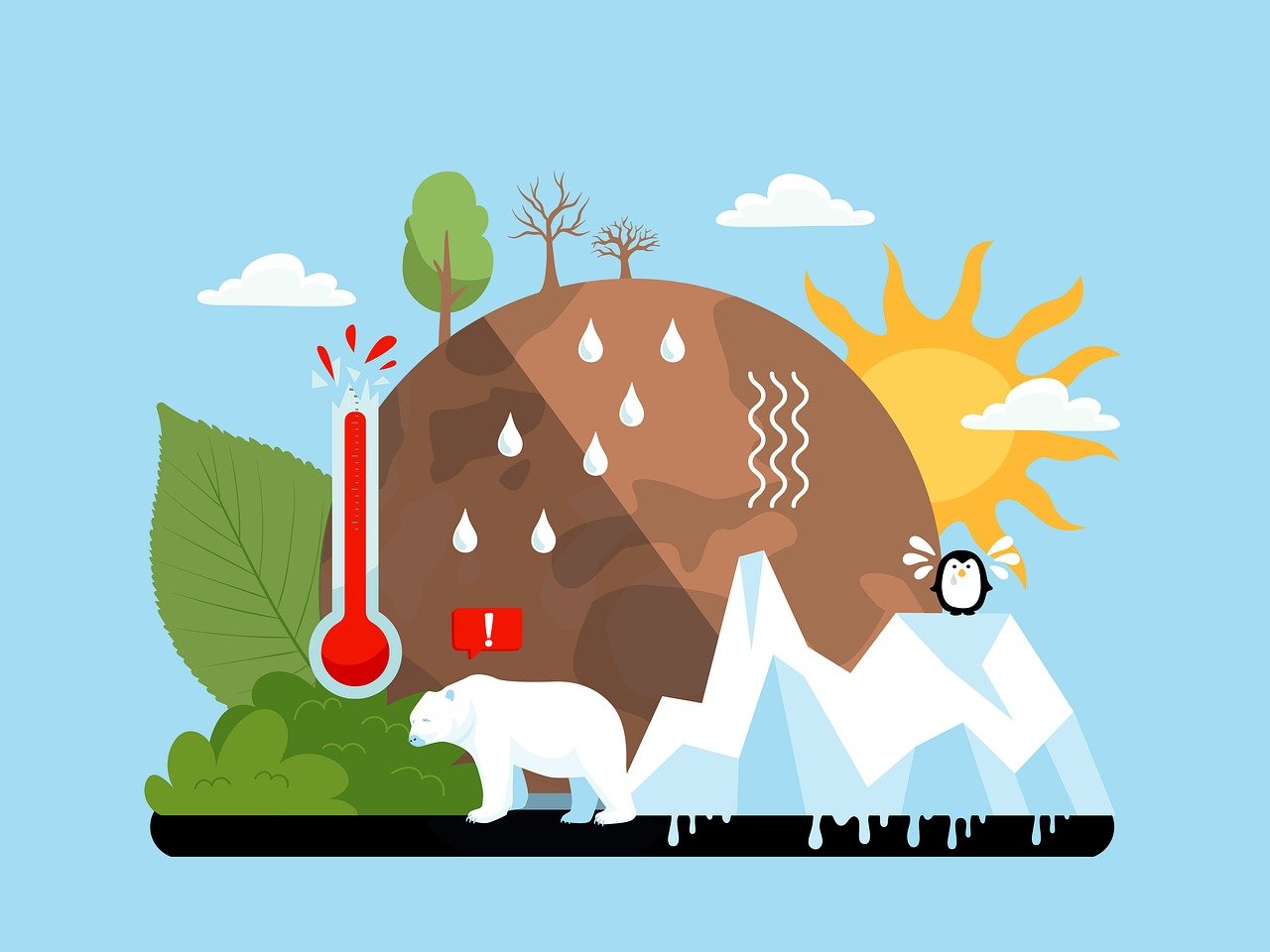

コメント