佐伯啓思『自由とは何か』(2004)
「自由」を問い直す
2004年刊行。
「自由」という身近でありふれた概念をその思想的な根拠から問い直している。今の日本であまりにも当然のものになりすぎて、切実感の失われた自由というものに対して、その意義を新たに見出すことが本書の主題だ。
自由の歴史的背景
著者はまず、「自由」という概念がどのような歴史的背景から生まれたのかを検討する。
近代的な自由の概念は、絶対王政のもとでの身分的な抵抗の中から誕生した。その後、この自由という概念は、さまざまな思想家の議論の中で彫琢され、「社会や国家から自立した自由な個人」という理念へと発展していく。
この近代的自由の本質は、「拘束・障害・抑圧からの解放」にある。そのため、近代思想において自由は、しばしば道徳や政治権力と対立するものとされてきた。
しかし、人が社会の中で生きる以上、道徳や権力は不可欠なものだ。ホッブスの社会契約論やカントの道徳律の議論は、人間の自由を絶対的な条件として認めた上で、いかにして権力や道徳を正当化させるのかという試みだったと言ってもいいだろう。
だが、カントの時代のような宗教的な背景を当てにすることが出来なくなった現代では、リベラリズムは、功利主義的な方法によってしか、道徳や権力を正当化できなくなっている。
行き詰まる自由の概念
ここに、現代リベラリズムが抱えるディレンマがある。
例えば、「最大多数の最大幸福」という原則を正当化の基準とすれば、多数派にとって有益とされることは、たとえそれが差別や虐殺であっても容認されかねない。また、自己の利益を放棄し、非合理的に行動する者を否定する根拠も持ち得ない。
つまり現代のリベラリズムには、「多数者の専制」や「破滅的な個人行動」に歯止めをかける思想的根拠が存在しない。もしリベラリズムが権力の正当化に失敗すれば、その先に残されるのは、全体主義かアナーキズムしかないのだ。
このようなリベラリズムの限界は、アメリカにおけるイラク戦争の正当化や宗教原理主義の台頭といったかたちで表れている。一方、日本では、教育の現場にその問題が現れた。
子どもたちが「殺人や売春も個人の自由だ」と言ったとき、大人たち(社会)はそれに反論できる論拠を持ち合わせていなかった。「個人の自由だから仕方がない」として、何もせず諦める——そんな無責任で無気力な大人の姿が、現代日本にはあふれていたのだ。
リベラリズムを超えて
佐伯氏の問題意識は、こうしたリベラリズムの限界をいかに乗り越えるか、という点にある。
著者はまず、バーリンの「消極的自由(〜からの自由)」を再評価する。しかし、消極的自由によって私的領域の保障や社会的多元性が担保されたとしても、それでも価値と価値の対立・抗争は残ると指摘する。
そこで佐伯氏は、個人より先に存在する「社会」、より具体的には「国家」というものを、個人が引き受ける必要があると説く。個人は無条件に存在し、自立しているわけではない。まずは、社会という土台に支えられているという事実を認めるところから始めるべきなのだ。
結局のところ、リベラリズムのディレンマを乗り越えるためには、「個人を超える存在」を導入するしかない。佐伯氏にとって、それが国家の持つ意味である。この考え方は、ある意味ではカントの道徳律とよく似た構成をしている。すなわち、国家は超越的な道徳律として、非常に世俗的な形で現れているのだ。
議論の展開について
著者の議論はこのあたりから、やや大づかみに展開していく印象を受ける。国家という存在を持ち出すことで、リベラリズムの限界を一挙に乗り越えようとするその構成には、やや急ぎすぎた印象も否めない。
確かに現代において、国家は個人の権利や自由を保障しつつ、必要な拘束を与える正当性を持つ、重要な枠組みであることは間違いない。
しかし、個人を超える存在として国家のみを特権化する立場には、なお慎重な検討が必要だろう。近代国家は、カントの道徳律のような普遍的なものではなく、あくまでも歴史的・社会的な経緯に基づく存在であり、状況に応じた便宜的な枠組みに過ぎないと見ることもできる。
たとえリベラリズムに理論的な限界があるとしても、それを乗り越える存在として国家をただちに位置づけるのは、やや短絡的とも言えるかもしれない。本来、国家はリベラリズムと対立するものではなく、その枠内での修正・補完的な機能として捉えられるべきである。
その意味で、リベラリズムの限界を真に乗り越えるためには、国家の正当性を理論的に支える根拠がより明確に示される必要がある。現時点では、著者の議論はリベラリズムの限界を指摘し、国家の意義を示唆するにとどまっているように思われる。
今後の課題へ
本書は新書という性格上、一定の制約があったことも影響しているのかもしれないが、著者の主張の中核はここまでで一段落しているように感じられる。その後の章では、リベラリズムをめぐるさまざまなエピソードや事例が紹介されている。(ケインズを中心とした20世紀初頭のケンブリッジ・サークルの話などは、非常に興味深かった。)
国家の正当性についての掘り下げは、別の機会に委ねられているという印象だ。
思索の意義と今後への示唆
著者が「個人を超える存在」の必要性に触れている点については、人命尊重や個人の権利を重視する現代の価値観からは、さまざまな異論も想定される。しかし、それでも著者の問題意識は、アメリカの外交政策や日本の教育現場への違和感を出発点とした、非常に現実的で誠実な思索に支えられているように思える。
この議論は、西欧的な人権思想をただ紹介・注釈するだけの議論とは明らかに異なり、自らの立脚点から思考を深めようとする姿勢に貫かれている。そうした意味で、本書は学術的な専門性に限らず、一般の読者にとっても大きな示唆を与えてくれる内容だと言えるだろう。
私たちが日々当然のように享受している「自由」というものについて、その正当性や意味を一度立ち止まって考え直してみること——それが本書を通して投げかけられている、静かながらも重要な問いなのである。
佐伯啓思『自由とは何か』(2004)


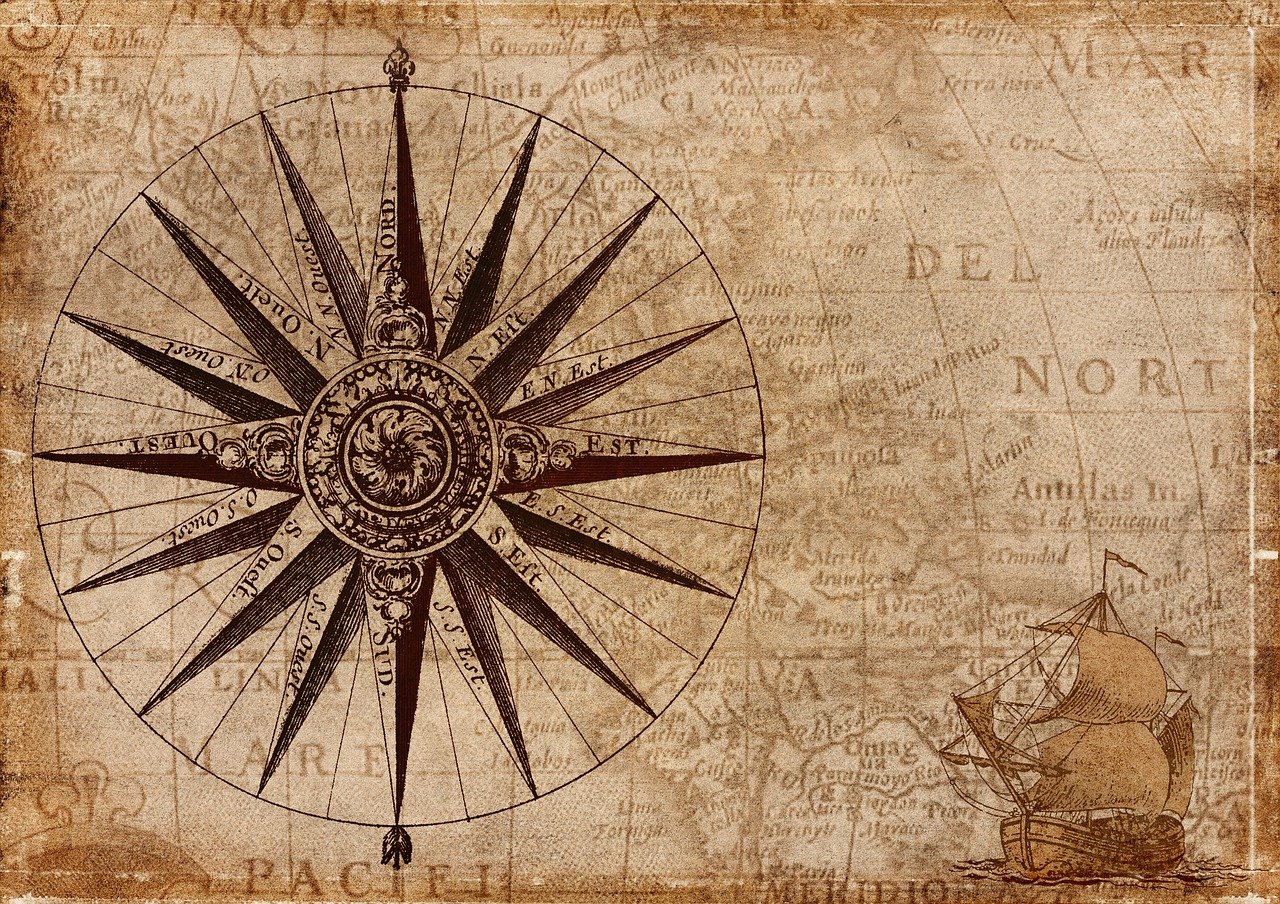
コメント