ネズミが頻繁に出るようになった東京。。。
最近、渋谷でネズミの目撃が話題になっている。
これほど大きな話題になっているのは、それだけネズミに馴染みのない人が多いということなのだろう。
ひと昔前——10年ほど前までは、普通に生活していてネズミを見かけるなんて、自分には考えられなかった。海外で初めてネズミを見たときは、思わず叫びそうになったのを覚えている。
それが、4〜5年ほど前から、「渋谷ではネズミがよく出るらしい」といった話をちらほら耳にするようになった。そしてここ2〜3年、自分自身も都内でネズミを見かけることが何度かあった。新宿では数回、中野と高田馬場でも1回ずつ目撃している。
ネズミは、本当に増えているのだろうか?
ネズミ被害の実態調査
東京都福祉保健局によると、都内の市区町村と保健局に寄せられたネズミ被害の相談件数は、1997年(平成9年)頃までが年間1万件ほど、それが2001年(平成13年)には、2万件近くとなり、倍増している。その後は、徐々に件数を減らし、2017年(平成26年)には7000件ほどになっている。
参考
・生活の衛生 ねずみ・衛生害虫 – 東京都保健医療局
・都民のためのねずみ防除読本 – 東京都福祉保健局
近年は、だいたい7000件前後で横ばいであり、特に増えているという訳ではないようだ。
ただし注意すべきなのは、この数字が「相談件数」であり、実際のネズミの個体数や被害件数を調査したものではないという点だ。都では、実態調査は、なんと!行ってないのだ。(相談件数の統計を取るだけの簡単なお仕事です)
都では、実態の把握はまったくなされていない。
そのため、実際、増えているのかどうかは分からない。
ネズミ問題の本質は「種類の変化」にある
とはいえ、相談内容から、近年のネズミ被害の特徴として、「ネズミの種類構成の変化」が起きていることが見て取れる。
人の生活圏に現れるネズミは「イエネズミ」と総称され、主に以下の3種が知られている。
・ドブネズミ
・クマネズミ
・ハツカネズミ
都市部の繁華街などに住み着くのは、主にドブネズミとクマネズミの2種類。昭和40年頃までは、ドブネズミの被害が圧倒的に多く、捕獲調査では90%がドブネズミだった。ドブネズミは、戦後の下水道や地下街の整備に伴って、個体数を増やしていったと思われる。
ドブネズミは屋外に住み着き、道端に出された生ごみなどを餌にして生活している。動きは鈍く、警戒心もそれほど強くない。そのため、殺鼠剤や捕鼠器による駆除で漸減していった。
それに代わって出てきたのが、クマネズミの方だ。現在では、ネズミ被害相談の9割がクマネズミによるものになっている。
クマネズミの場合、ドブネズミとは異なり、屋内に巣を作って住み着く。70年代から大型ビルの建築増加に伴って、ビル内に住み着き始めて、増えていった。
クマネズミは、動きが俊敏で、警戒心が極めて強い。そのため捕鼠器による捕獲が困難で、駆除が進まなかった。
さらには、殺鼠剤が効かない「耐性個体」も出現しており、いわば“スーパーラット”と化している。
多剤耐性菌ならぬ、「多剤耐性ネズミ」が都心部で勢力を広げているのだ。
有効な対策は「環境の改善」のみ
このような背景から、もはや従来の駆除方法だけでは、クマネズミの被害を食い止めることは難しくなっている。
現在、効果的とされる対策は、以下のような「環境改善」によるものしかない。
- 建物の侵入経路を塞ぐ
- 生ごみの管理や廃棄方法を徹底する
つまり、ネズミを「駆除する」のではなく、「寄せつけない」ための環境整備こそが重要なのだ。
見えてこない実態と行政の不作為
都内でネズミが増えているのではないか――そう感じる人は少なくない。
だが、その実態は行政によって正確に把握されていない。今あるのは、相談件数という限られたデータのみ。実数の調査も分析も行われておらず、私たちは“肌感覚”でネズミの存在を感じ取るしかない状況だ。
おそらくは、都市部におけるごみ処理の変化、清掃体制の問題、大型ビルの老朽化など、複数の要因が絡み合い、ネズミの被害が身近になっているのではないか。
問題の本質は、「数の問題」だけではなく、「都市の構造と行政対応の限界」にあるのかもしれない。
ネズミ対策として私たちにできること
景観・衛生の意識の低さ
東京などの都市部では、路上にゴミを出す光景が日常となっている。狭い歩道に積み上げられたゴミ袋の山は、誰もが見慣れた風景だろう。
しかし、それはネズミやゴキブリにとって、格好の餌場でもある。都市環境そのものが、こうした害獣を引き寄せる要因となっているのではないか。


このような状況に対し、「不衛生である」「景観を損ねている」と感じる人が少ないことも、問題の根深さを示している。改善の必要性が市民の間に広く共有されているとは言い難いため、結果として、政治的な優先順位も低くなっているのが現状だ。
食品廃棄の構造的問題
加えて、コンビニエンスストアやフランチャイズの飲食店の増加も、都市の食料廃棄物の量に影響を与えている。これらの店舗では、深夜や閉店間際でも常に商品がそろっていることが「サービス」とされ、大量の仕入れと、それに伴う大量の廃棄が常態化している。
企業本部はフランチャイズ店舗に対して、過剰な仕入れを求める傾向がある。本部側は卸した時点で利益が確定するため、売れ残りによる廃棄が発生しても、経営上の損失とはならない。この構造が結果として食品ロスを増やし、ひいては都市のネズミ問題を助長している可能性がある。
こうした課題に対し、企業側にもより強い社会的責任が求められている。近年は「食品ロス削減」への関心も高まってきており、持続可能な流通・販売のあり方が、あらためて問われている。
根本的な対策は「ごみの管理」
ネズミは、人間の出す生ごみを餌にして繁殖する。したがって、ネズミ被害を抑える根本的な手段は、最終的には「ごみの出し方」「ごみの管理」にかかっている。
特に都市部では、ごみの排出量を減らす努力とともに、管理の徹底が求められている。
現在は、繁華街を中心にネズミの被害が見られるが、1990年代以降、一般家庭での被害報告も増えつつある。今後、適切な対策を怠れば、私たちの生活空間にネズミが入り込むリスクも現実のものとなりかねない。
私たちにできること
では、私たちは何をすべきなのか。
まず、議員や役所に対して、ごみ処理の方法や環境改善に関する要望や意見を継続的に届けることが重要だ。意見は、電話やメールなどを通じて伝えることができるし、多くの自治体や議員はウェブサイト上で市民の声を募集している。
税金を負担している市民として、こうした声を届けることは当然の権利であり、社会参加の一つでもある。
また、企業の姿勢にも目を向けるべきだ。食品廃棄の問題に対して十分な対応をしていない企業に対しては、消費者として「選ばない」という行動をとることも、メッセージとなるだろう。日々の買い物が、都市環境に与える影響を考える視点が求められている。
個人でできることから、一歩ずつ始めていくべきだろう。
自分の部屋でネズミを見ることになる前に!
追記
でも、実際、自分の部屋でネズミを見たらどう対処すればいいんだろうか?
🐀🐀🐀))))))
捕まえる?叩いてつぶす?出て行くまで待つ?
どーすりゃ、いいんだ?
ゴキブリ以上の病原菌を媒介する。ノミを拡散する。噛まれたら感染症にかかる。こんな生物兵器。。。勝てる気がしない。。。

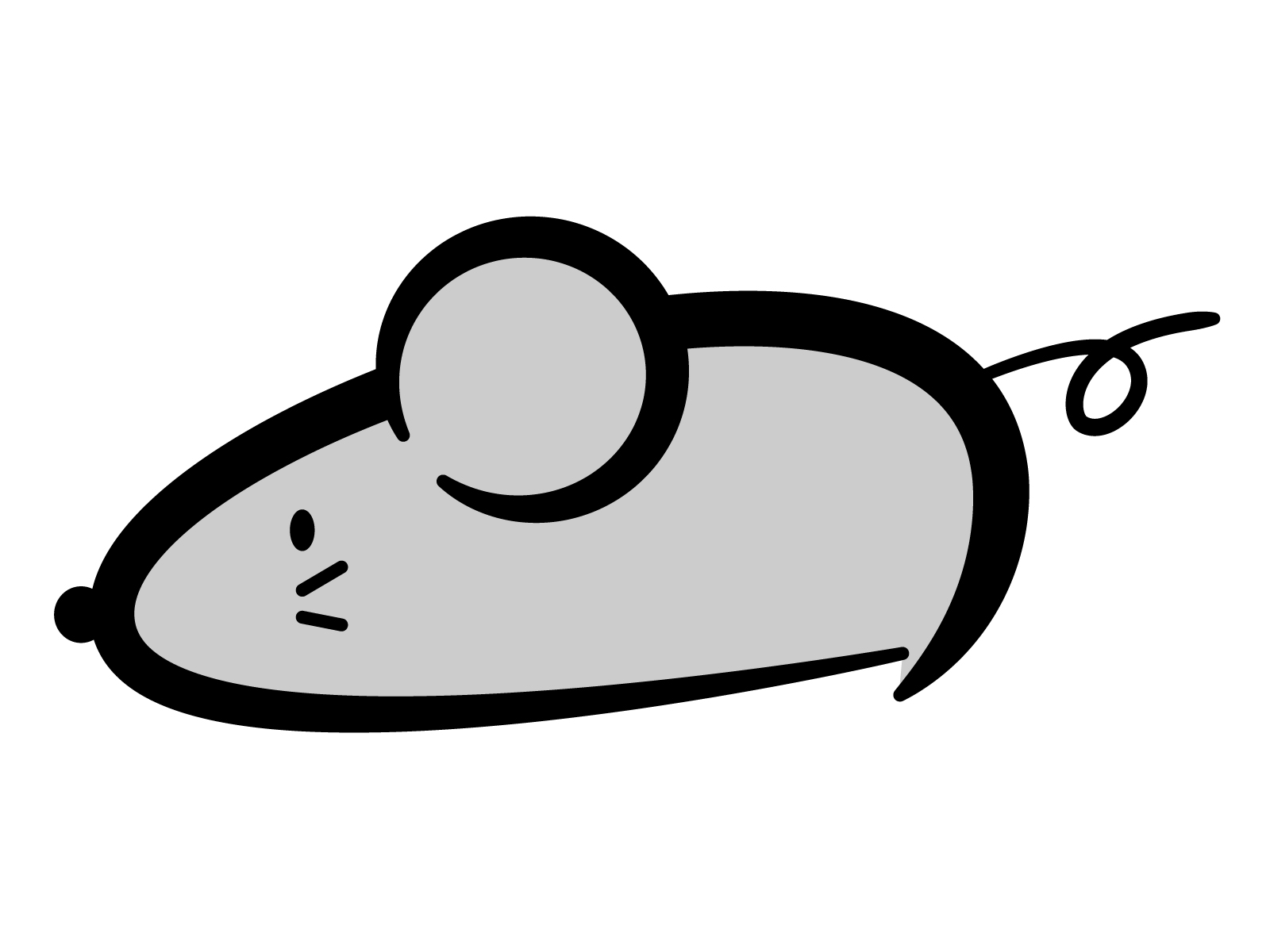

コメント