ゲノム編集食品、ついに市場解禁へ──拙速な決定と国民不在の議論
日本が世界に先駆けて、ゲノム編集食品の一般市場での流通を許可しようとしている。厚生労働省は今年3月末、新開発食品調査部会にて、ゲノム編集食品の扱いに関する報告書を提出し、その中で一般販売を認める方針を明確にした。
この報告書は、ほとんど議論を経ることなく結論ありきでまとめられており、国会での審議も国民への十分な説明もないまま、行政判断のみで解禁に向けて動いている。市場への流通は、早ければ今年8月にも始まる見込みだ。
しかし、この政策決定には重大な問題がある。第一に、ゲノム編集食品の安全性については、科学的な合意がまだ得られていないという現状がある。実際、アメリカやEUでは、ゲノム編集食品の販売は認められておらず、欧州司法裁判所は2018年に「遺伝子組み換え食品と同様の規制が必要」と判断している。
第二に、制度整備と民主的な手続きの欠如が挙げられる。本来、こうした重要な政策変更には、関連法案の整備や国民的な議論、国会での審議が不可欠だ。しかし、今回の対応ではそのような手続きがすべて省略されており、拙速と言わざるを得ない。
欧米諸国をはじめ各国でまだ認められていない新技術を、世界に先駆けて日本国内で流通させることには、大きな懸念が残る。このままでは、日本人が事実上の「実験台」とされることになりかねない。ゲノム編集食品の解禁は、拙速にではなく、慎重に進められるべきである。
ゲノム編集食品と遺伝子組み換え食品──「安全性」判断の根拠は十分か
厚生労働省の新開発食品調査部会は、今年3月末の報告書において、ゲノム編集食品について「安全性に問題はない」との結論を示した。しかしこの判断は、食品としての臨床試験や長期的な実証実験を経たものではなく、あくまで理論的な推定に基づくものである。
ゲノム編集と遺伝子組み換えの技術的違い
調査部会は、ゲノム編集技術を従来の「遺伝子組み換え(GMO)」とは明確に異なるものとして扱っている。GMOでは、特定の目的のために他の生物の遺伝子を導入する操作が行われ、自然界では起こりえない遺伝子構成が作られるのが特徴である。
対して、ゲノム編集技術(特にCRISPR-Cas9)では、生物自身の遺伝子の一部を切断・修復することで突然変異を誘導する。CRISPR-Cas9は、細菌が持つ獲得免疫システムに由来する技術で、ガイドRNA(gRNA)を使ってDNAの特定箇所を認識し、Cas9酵素がそこを切断することで、狙った遺伝子改変を実現する。この技術は高精度かつ低コストで操作が可能なため、農作物や畜産物への応用が急速に進んでいる。
しかしこの「精度」はあくまで相対的なものであり、オフターゲット変異(意図しない箇所への遺伝子変化)の可能性は完全に排除できない。しかも、その変異が食品として消費された際に人体にどのような影響を及ぼすかは、長期的な摂取と世代を超えた評価なしには明らかにならない。
安全性判断をめぐる各国の規制状況
国際的に見ても、ゲノム編集食品の規制には大きなばらつきがある。
- 欧州連合(EU)では、2018年に欧州司法裁判所が「ゲノム編集は遺伝子組み換え技術に該当し、同様の規制を受ける」との判決を出し、GMOと同等の厳しい承認プロセスが義務付けられている。
- アメリカでは、食品医薬品局(FDA)や農務省(USDA)がゲノム編集作物の商業化を検討中だが、現在のところ一般流通に向けた包括的な認可は下りていない。一部の作物(例:高GABAトマト)は例外的に流通しているが、それでも事前の申請と評価手続きが求められる。
- 中国ではゲノム編集研究は活発だが、食品としての商業利用については依然として試験段階にあり、正式な市場解禁には至っていない。
このように、世界の主要国は、安全性への懸念から慎重な検証と規制の整備を優先しているのが現状である。
日本の政策判断は拙速ではないか
こうした国際的な動向と比べると、日本の政策決定はあまりにも早く、また透明性に欠ける。国会での審議もなされず、国民的議論も不十分なまま、厚労省の部会報告書を根拠に行政判断のみで市場解禁を進めている。
ゲノム編集によって得られた突然変異が、長期的にどのような健康影響や生態系への影響を及ぼすかについては、いまだに不明な点が多い。たとえ短期的に「安全」とされても、それが未来にわたって保証されるものではない。
日本が世界に先駆けてゲノム編集食品の解禁を進めることは、実質的に国民を「実験対象」として扱うリスクを伴っている。技術の可能性を否定するものではないが、その実装には科学的根拠と民主的手続きの両立が不可欠である。
野放しにされるゲノム編集食品──制度不備と説明責任の欠如
諸外国がゲノム編集食品の取り扱いに慎重な姿勢を示す中で、日本の厚生労働省の対応は、際立って異質である。あらゆる判断が、「ゲノム編集食品は安全である」との前提のもとに進められており、その前提自体に対する科学的・民主的な検証がほとんど存在しない。
審査も届け出も表示も不要──制度の実態
厚生労働省および消費者庁が示したゲノム編集食品の扱いは、以下のとおり極めて規制が緩い。
- 個別食品に関して安全審査は不要
- 販売にあたっての届け出は任意
- 表示義務はなし
これらは、事実上の“野放し状態”である。科学的な安全性が十分に確認されていない段階で、流通・消費を完全に市場の自由に委ねる政策は、消費者保護の観点から極めて問題がある。
消費者の「選ぶ権利」を奪う制度設計
特に重大なのは、表示義務が課されていないという点である。仮に安全性に議論があっても、消費者が「食べるかどうか」を自ら判断するための情報を提供する義務は、最低限の制度的保障であるべきだ。
消費者庁は、表示義務を課さない理由として「ゲノム編集による変異と自然突然変異の区別が技術的にできない」と説明している。しかし、実際には、ゲノム編集操作は研究段階で詳細に記録されており、製造・流通の段階で管理することは可能である。技術的に不可能なのではなく、制度としてあえて管理しない判断をしているというのが実態に近い。
この判断は、業界団体や行政の都合を優先し、消費者の知る権利・選ぶ権利を軽視するものであり、透明性を欠いた行政運営の典型例である。特定の立場に偏った政策決定が行われている背景に、省庁間の忖度や政治的圧力があるのではないかとの疑念も拭えない。
問われる説明責任と市民の自己決定
厚労省や消費者庁の説明は、しばしば専門用語を用いた一方的な発信に終始しており、市民に対する理解促進や情報公開の姿勢が著しく不足している。本来、行政には、科学的根拠とともに、市民が納得できるような情報提供を行う義務がある。
何より重要なのは、市民一人ひとりが自ら判断し、自ら選ぶ力を持つことである。行政が十分に情報を提供しない以上、私たちはメディアや市民社会の情報を活用し、判断力を高めていくしかない。食の安全に関わる決定を、専門家や役所任せにせず、「自己決定権」を行使する市民の成熟した姿勢が、今こそ求められている。


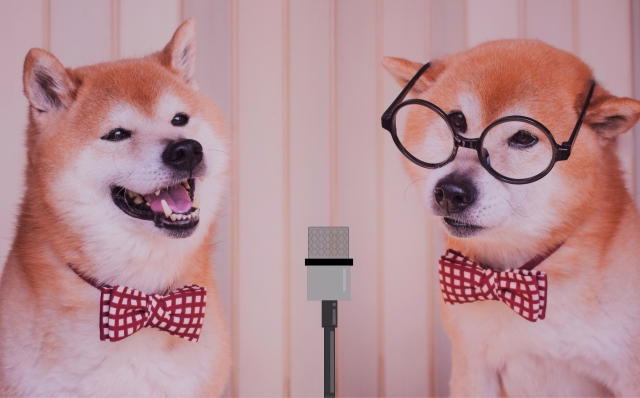

コメント