茂木健一郎『クオリア入門 ― 心が脳を感じるとき』(2006)
クオリアへの新しいアプローチ ― 反応選択性の再検討
私たちの心の中のすべての表象は、クオリアという単位からできている。
意識研究において、クオリアの問題は中心的な位置を占めている。脳の物理的活動が意識に関与していることは、神経科学的な観察や臨床的知見から広く支持されている。しかし、特に「何かがどのように感じられるか」という主観的な体験、すなわち第一人称的な感覚がどのようにして生まれるのかについては、いまだ明確な理論的説明が存在しない。
脳内では、特定の刺激に対して特定のニューロンが反応する「反応選択性」と呼ばれる性質が知られている。たとえば、リンゴを見たときに毎回「リンゴだ」と認識できるのは、視覚情報に対して安定して反応するニューロン群が存在するためである。このような神経応答の再現性は、我々の知覚が一貫したものとして成立する基盤をなしており、脳の情報処理の信頼性を支えている。
反応選択性は、神経科学において豊富な実証的データによって裏付けられており、脳の情報処理メカニズムの理解において重要な役割を果たしてきた。しかし、著者はこの反応選択性の考え方だけでは、クオリアの本質に迫ることはできないと指摘する。なぜなら、ある刺激に対してニューロンが反応するという事実が、必ずしもそのときに「どのような体験が生じるか」という問題、すなわちクオリアの内容に直結するとは限らないからである。
もしクオリアを単なる神経反応の副産物と捉えるならば、心の働きはニューロンの活動に従属する受動的なものとして説明されてしまう。このような立場では、心の能動的な側面——意志や選択、主体的な知覚の在り方——が見落とされる可能性がある。
こうした立場に対して著者は、因果的な刺激-反応の枠組みを超え、ニューロン同士のネットワーク的な相互関係に着目すべきだと提案する。これは、全体の構造が個々の要素のふるまいに影響を与えるという「マッハの原理」にヒントを得た発想である。そして、反応選択性に過度に依拠する態度を「ひとつのドグマにすぎない」として批判している。
志向性とポインタによるクオリア理解の再構築
反応選択性に代わる視点として、著者が提示するのが「ポインタ(志向性)」という概念である。私たちが知覚する内容は、感覚器官からの生の情報そのものではなく、脳内で一定の処理を経て構成されたものである。
このことを端的に示すのが「両眼視野闘争」という現象である。左右の目に異なる映像を提示すると、脳は両方を同時に意識するのではなく、片方の映像を優先して知覚する。このとき、見えている内容は右目や左目の映像そのものではなく、それらを統合・解釈した新たな「第三の映像」として現れる。著者は、この知覚の変化を説明するのが「ポインタ」という考え方であるとする。
ポインタは、主観的に知覚されるクオリアに対して、より抽象的で認知的な枠組みを提供する概念である。視覚や聴覚といった感覚情報は、脳内で単に再現されるのではなく、文脈や意味づけを通じて解釈される。この解釈のプロセスには、知覚する主体の関与——つまり能動的な心の働き——が不可欠である。
著者は、ポインタという概念を通じて、「心の主体性」や「志向性(ある対象に向かう心の働き)」の再評価を試みている。これは、クオリアを単なる神経的反応ではなく、主体的な意味構成のプロセスとして捉え直そうとする試みであり、従来の神経科学的アプローチに対する重要な補完となりうる。
不明瞭な結論
本書はおおむね上述したような議論の流れで締めくくられている。著者が、従来の枠組みにとらわれず新たな視点を提示しようとしている意図は十分に理解できる。しかし、クオリアの問題からポインタの概念へと展開する過程において、実証的な裏付けに乏しいまま、抽象的な概念説明が中心となっている点には慎重な検討が求められる。
とくに、「ポインタは志向性の概念と同じである」という結論に至るくだりでは、19世紀の哲学者による議論が唐突に引用され、読者にとってはやや論理の飛躍を感じさせる構成となっている。著者自身、ポインタや志向性が「主体性を考える上で重要な鍵となる」と述べているが、それが脳内のどのような機能やプロセスに基づいているのかという点については、明確な科学的説明がなされていない。そのため、ポインタや志向性が具体的にどの神経メカニズムと関連しているのかが読者には把握しづらく、理論の実体がつかみにくくなっている。
また、議論の終盤では、哲学的な整理に重きが置かれ、最終的には「やはり心と脳の関係はハード・プロブレムとして残る」といった形で結論づけられている。この構成は、問題の複雑さを強調する一方で、読者にとっては論点が曖昧になった印象を受けるかもしれない。
加えて、著者のこれまでの幅広い活動を踏まえると、専門外の領域にまで議論を広げるスタイルには賛否が分かれるだろう。メディア出演や多様な著作活動を通じて広く発信を続ける姿勢は評価できる一方で、時に、まだ科学的に確立されていない知見を含めて「脳の働き」と結びつけすぎてしまう印象も否めない。
たとえば、「脳の活性化に役立つ」といった断定的な表現には、慎重さが求められるだろう。思考や作業によって脳の血流が一時的に増加するのは自然な生理現象であり、それをもって「脳が活性化された」と言い切ることが妥当かどうかについては、さらなる議論が必要である。
参考
・アハ体験
茂木健一郎『クオリア入門 ― 心が脳を感じるとき』(2006)
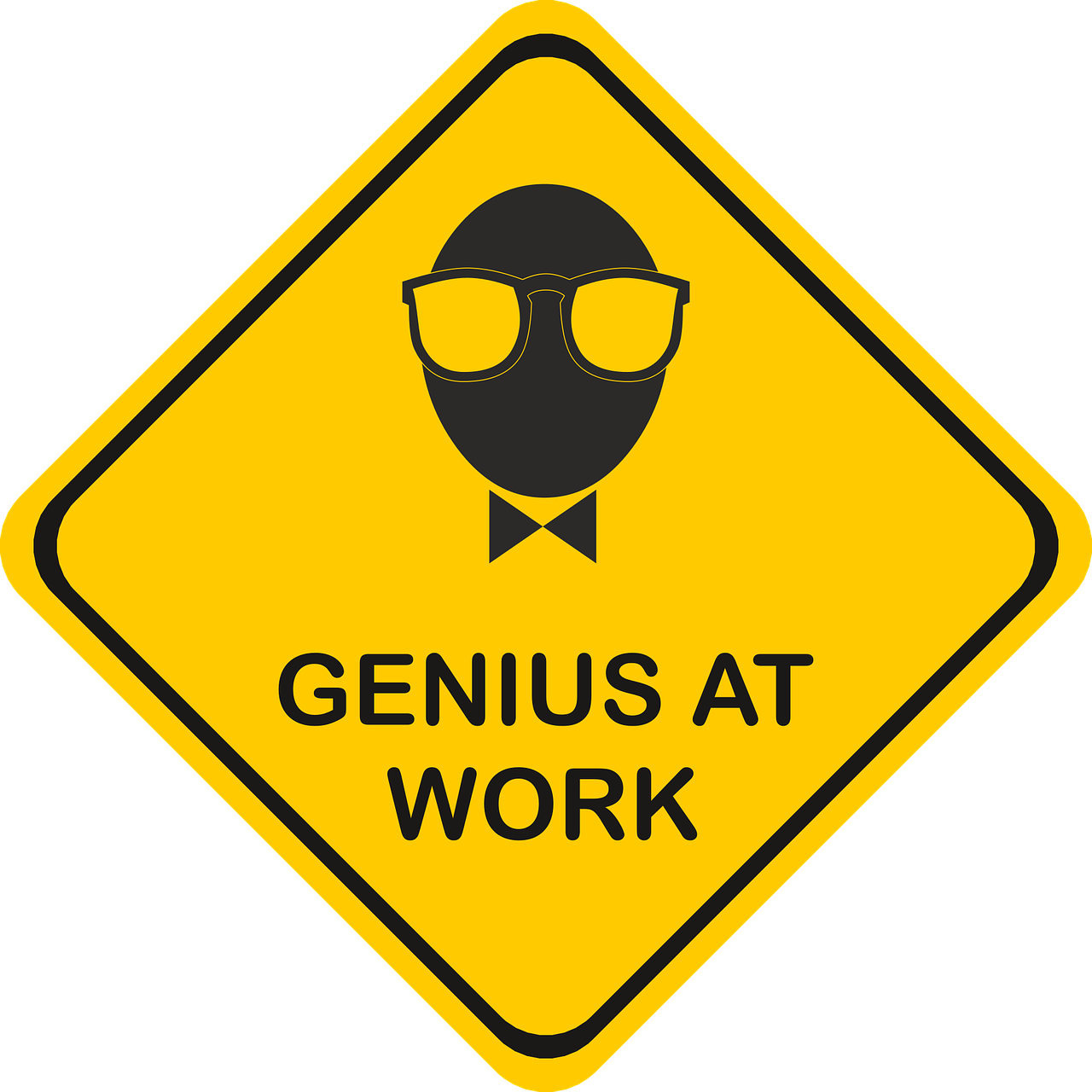


コメント