郊外化——古くて新しい課題
日本では高度経済成長期、特に1960年代から70年代にかけて、急速に郊外化が進行した。「郊外化」とは、都市中心部に集積していた居住、商業、行政、医療などの機能が、都市周辺部へと分散・移転していく現象を指す。
この郊外化の進展により、地方の中小都市では中心市街地の空洞化が進み、かつて賑わっていた商店街や公共施設は衰退。人口や機能が周辺部へと薄く広がる形で拡散し、結果として生活圏の広がりに対し、交通インフラの整備が追いつかず、自家用車に依存する生活スタイルが定着することとなった。
この問題は決して新しいものではない。1970年代からすでに指摘され続けてきたにもかかわらず、抜本的な対策は後回しにされ、日本はこの都市構造の歪みに数十年にわたって向き合わずにきた。
しかし近年、再びこの問題が注目されつつある。理由は、人口規模の大きい団塊の世代(1947〜49年生まれ)が70代を迎え、自動車の運転能力に支障をきたし始めていることにある。車に依存して生活してきた高齢者にとって、運転ができなくなるということは、すなわち「移動手段の喪失」を意味する。これは買い物や通院といった日常生活そのものが成り立たなくなることを意味し、深刻な社会問題となりつつある。
高齢者の移動手段の危機
近年、高齢ドライバーによる交通事故のニュースが相次いでいる。これを受け、運転免許の自主返納を促す取り組みや、高齢者への免許定年制導入の是非をめぐる議論も行われている。しかし、多くの高齢者は返納に強く抵抗している。それは、車を手放した瞬間に、生活の自由度やQOL(生活の質)が著しく低下するという現実があるからだ。
特に、公共交通機関の選択肢が限られた地方郊外では、この問題は都市部以上に切実である。移動手段を失うことで、孤立や生活困窮、場合によっては医療アクセスの途絶すら引き起こしかねない。
海外の都市が示すヒント——機能の再集約による都市再生
一方で、欧米諸国では同様の郊外化・モータリゼーション(車社会化)に対して、1970年代以降、積極的な対策が講じられてきた。
たとえばドイツのミュンヘン、フランスのルーアン、アメリカのミネアポリスなどが有名な事例だ。それらの地域では、都市の機能を再び中心部に集約させ、持続可能で人にやさしい都市構造への転換が進められてきた。
都市計画の基本方針は、以下のようなシンプルな原則に基づいている:
- 歩行者が安心して自由に移動できる区域(ペデストリアンゾーン)を都市中心部に設ける。
- その区域内に、医療・行政・商業などの都市機能を集中的に配置する。
- 郊外や周辺地域からでもアクセス可能な公共交通機関を整備・拡充する。
これらの施策によって、都市中心部の活性化と郊外の生活利便性の両立が実現されつつある。特筆すべきは、「車なしでも生活できる都市」を目指した政策によって、高齢者や子育て世代、観光客など多様な層にとっても快適な環境が提供されている点である。
それでも動かなかった日本——対策なき都市政策の末路
しかし一方の日本では、地方議会も行政も、郊外化への抜本的な対策をほとんど講じてこなかった。都市の構造が変化し、高齢化が進行する中で、都市計画の再設計という本質的な議論は先送りされ続けてきたのである。
「郊外化」という半世紀以上も前から認識されてきた社会問題を放置し続けた結果、そのツケがいま、私たちの足元にのしかかってきている。車社会と高齢化社会という二重の構造的変化が同時に進行する中で、公共交通の空洞化と生活圏の拡散に歯止めがかからず、「移動弱者」あるいは「交通難民」と呼ばれる人々が急増している。
これは単なるインフラの老朽化や財政の問題ではない。都市計画の欠如、ビジョンなきまちづくり、そして政治の無策が生んだ人為的な問題である。
そろそろ本気で、この国の「街のかたち」を見直すべき時が来ている。郊外への無計画な拡張と、都市中心部の空洞化という流れに歯止めをかけ、機能を再び集約するための明確な都市ビジョンと政策が求められている。
【今こそ必要な転換】
- 郊外の生活圏における公共交通の再整備
- 都市中心部への医療・行政・商業機能の再集中
- 高齢者・子育て世代を含む多世代にとっての住みやすい都市構造への転換
- 地方議会や住民自身が主体的に都市の未来像を描くしくみの構築
「都市は生き物」である。変化する環境や人口構造に応じて柔軟に進化していかなければ、その生命線である「暮らしやすさ」も「持続可能性」も失われてしまう。
郊外化という“古くて新しい問題”は、まさに今、私たちに「どんな未来の街をつくるのか」という問いを突きつけている。


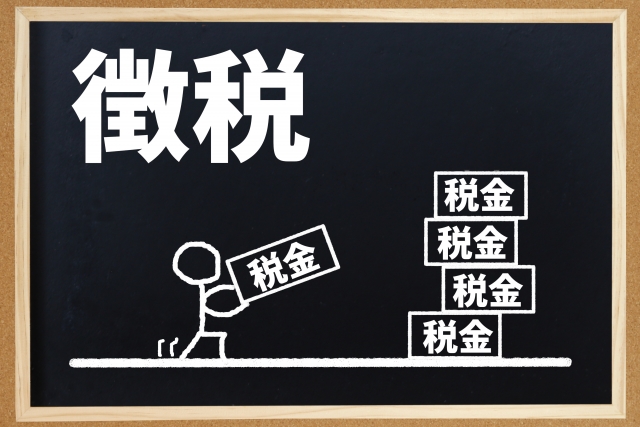
コメント