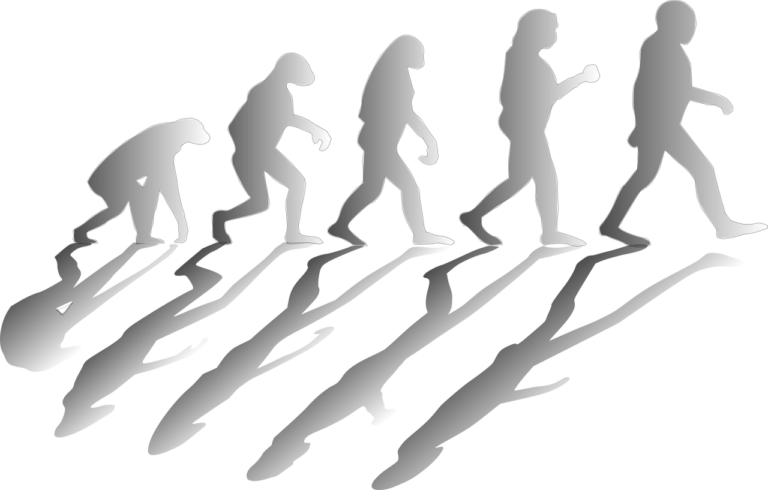19世紀の歴史哲学
19世紀、ヨーロッパでは「歴史」をどう捉えるかという問いが、思想家、哲学者たちの間で主要な問題となっていた。
社会変動を科学と人間精神の発展過程として捉えたフランスのオーギュスト・コント、社会進化論を提唱したイギリスのハーバート・スペンサー、歴史の発展を貫く法則として弁証法を論じたドイツのヘーゲル、そのヘーゲルの歴史観の影響を受けて、社会経済の発展史観を展開したマルクス。
彼らの思想は、「歴史の発展」をどう解釈するかという問いから生まれていった。「歴史哲学」の誕生だった。
進化論もそのような歴史哲学の流れの中で、生物を「歴史」として捉えようとした一つの思想として登場した。生物を時間の相で捉えること、つまり、生物の歴史学として登場したものが進化論だった。
18世紀までは、生物は種として誕生し、その種のまま決して変化することはないという神学的な理解が一般的だった。しかし、化石の研究を中心として、生物の歴史的変化が論じられるようになると、種が変化するという進化についての考え方が広がっていった。
そして、1859年、チャールズ・ダーウィンによって、『種の起源』が出版された。
その後、生物学では、実証科学として、生物の歴史的変化の要因や法則を解き明かそうとする研究が進められてきた。
進化論も歴史の中で進化している。ここでは進化論の進化史を辿ってみよう。
初期進化論
ジャン=バティスト・ラマルク
用不用論 (1809)
後天的に獲得された形質が子孫へと遺伝するという思想。『動物哲学』の中で主張された。
生物は、自らが置かれた環境や自己の選択的意思によって、器官や体の部位の使用に頻度や強度の差が生じている。その結果、生物の器官は、その使用・不使用の頻度差によって発達もしくは退化し、各器官の形質が後天的に獲得されていく。この獲得形質が子孫へ遺伝すると考えられた。
獲得した形質によってより環境に適応したものが、遺伝によって世代を重ねることで、さらに有利な方向へと進化する。
ラマルクはこの考えを基に、生物は自然発生し、単純なものから複雑なものへという目的論的に進化する、という生物進化論を主張した。
進化論の成立
チャールズ・ダーウィン
自然選択説 (1859)
『種の起源』の中で発表された思想。現代の進化論の基礎となる考え方。原語は、”Natural Selection” であり、「自然淘汰」という訳は誤り。
食料など、生物が生きていくために環境から得られる資源は限られていて、全ての生物が生存・繁殖するために必要十分な量を賄うことはできない(自然界における資源の供給不足、需要過多)。そのため、生物には常に環境から淘汰圧がかかっている。
生物の個体は同種間でも、それぞれが持つ形質や性質に若干の差がある。このわずかな差が、繁殖する期待値に差を生じさせることになる。その中で環境に適応し、有利な形質を持った個体、種が、繁殖に成功する。
ダーウィンは、進化は偶然の結果が累積したもので方向性を持たないと主張し、目的論的解釈を否定した。
遺伝子の発見
グレゴール・ヨハン・メンデル
メンデルの法則 (1865)
植物の各形質が独立して遺伝することを発見(分離・独立の法則)。個別に遺伝する因子の存在を予想し、「遺伝子」の概念を導入した。この考えにより、獲得形質が遺伝することを否定した。
ウォルター・サットン
染色体説 (1902)
遺伝子が染色体上にあるという説を提唱。
生殖細胞が減数分裂することを観察した。
ネオダーウィニズムの登場
ロナルド・フィッシャー
総合説 (1930)
『自然選択の遺伝学的理論』の中で、ダーウィンの自然選択説が遺伝子の考え方と矛盾することがないことを示し、遺伝学と自然選択説を統合した。
生物の種や個体に形質や性質の差が生じるのは、遺伝子の突然変異であり、それが環境適応の期待値に差を生じさせる。
集団遺伝学
生物進化の予測と実証に数理モデルを導入。
環境適応や種分化といった遺伝による進化の過程を確率論や統計学など数学的手法を用いて、数理モデルによって研究。
現代進化論の発展
1940年代以降、進化論は、自然選択と突然変異を中心として、生化学、統計学、数理社会学、生態学などの研究成果も取り入れ、より広い学際的枠組みが成立していった。
オズワルド・アベリー
DNA遺伝子論 (1944)
遺伝子の実体がDNAであることを証明。DNAが形質転換の原因物質であることを突き止める。
分子生物学の成立。
V. C. ウィン=エドワーズ
郡選択説 (1962)
アリやハチなど個体を犠牲にして種を守ろうとする社会性の昆虫の事例から、自然選択は、個体間ではなく、種や群れの間にもっとも強く働くと主張。「利他的な」振る舞いをする個体が多い集団が存続しやすいとした。
郡選択説は、現在ではほとんど支持されていないが、自然選択における淘汰圧の対象(範囲)となるものは何か、という議論を引き起こした。また、生物にとっての「利他的」「利己的」というのが、一体、何に対する、どの次元についてのものなのか、という問題を提起し、後の行動生態学に影響を与えた。
以降、曖昧に語られていた自然選択に関して、その対象の厳密な定義が求められるようになった。
W. D. ハミルトン
血縁選択説 (1964)
生物個体ではなく、互いに繁殖可能な集団としての遺伝子給源(gene pool)を対象とし、その血縁集団を基準とした環境適応度を考える。
遺伝子を共有する血縁個体の繁殖成功を増すことによって得る間接適応度と個体の適応度を足し合わせた包括適応度を最大化する形質が進化する。
寄生者説
有性生殖の進化論的意義を説明する理論。
有性生殖は単性生殖よりも配偶者の確保など、生殖のための時間、労力、資源を必要とし、不利な状況にあるが、脊椎動物のほぼすべてが有性生殖をおこなっている。有性生殖が進化の過程で多くの種に広がっていった理由は、遺伝的多様性を促進させることに利点があったからだが、この有性生殖による遺伝的多様性の確保が、特に寄生体への対抗戦略として有効だったという説。
寄生者(寄生虫、ウイルス、細菌など)と宿主の間で、恒常的な軍拡競争が存在している。寄生者は一般的に宿主よりも寿命が短くより早く進化するため、常に淘汰圧がかかる。
宿主となる生物は、有性生殖による組み替えで、常に遺伝的多様性を増加させ続けることが、寄生者へ対抗手段になる。有性生殖は寄生体への対抗戦略である。
ヴァン・ヴェーレン
赤の女王仮説 (1973)
捕食者と被捕食者との間の関係を軍拡競争のようなものとして捉えた考え方。
捕食者と被捕食者との間には、互いの生存をかけた競争が常に存在し、そのため、種に対して永続的に選択圧がかかる。生物が生存競争(他種との競争)で有利であり続けるためには、常に進化によって継続的な改善が迫られることになる。
この説の名前の由来は、「同じところに立ち止まっていてはいけない。その場に留まる(現状を維持する)ためには、全力で走り続けなくてはいけない。」という『鏡の国のアリス』に登場する赤の女王のセリフから。
生物は、進化の中で生存に巧みになっていくわけではなく、生物分類上の科が絶滅する確率は、ランダムであることを主張した。