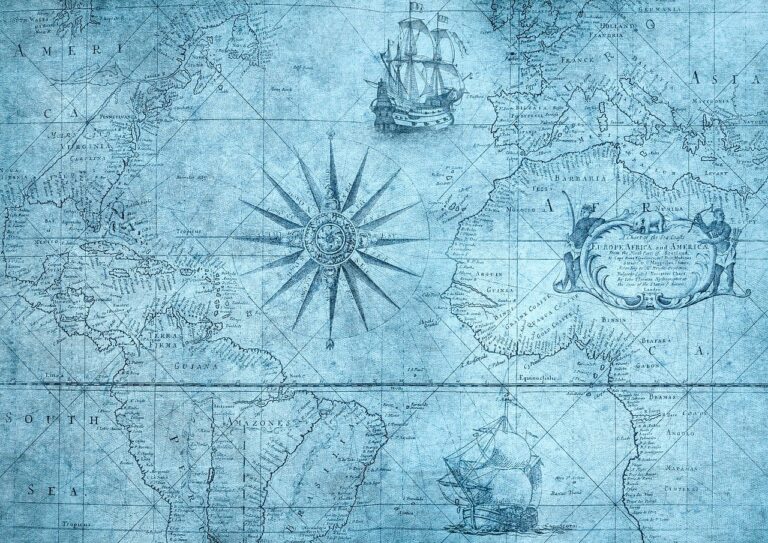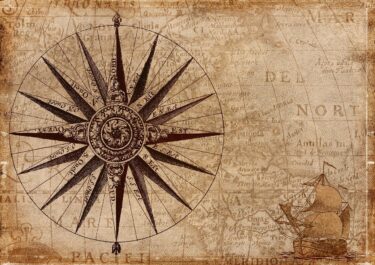読書案内
ジャレド・ダイアモンド『銃・病原菌・鉄』(1997)
歴史に見え隠れする自己正当化
環境要因説に基づいた壮大な人類史を展開した著者だが、この歴史観には一つの問題が指摘されている。帝国主義による世界の植民地化、奴隷貿易、原住民の虐殺などの歴史をどう評価するのかという問題だ。本書の理論では、これを必然的なものに読み替えていくことができるようになる。
歴史には、どうしてもこのような「史観」に関する問題が避けられない。
インディアンの人口激減は、病原菌に対する耐性の獲得に遅れていたからだ。オセアニア地域の発展が遅れたのは、農耕文化が根付かなかったためだ。発展の遅れた地域から文明が先行して発達した地域への富の集中が起こる。等々。
西欧諸国は文明の先進地域であり、世界中の富を保有している。そして、この富の偏在と発展段階の差を生んだものは、環境差であることを証明することで、西欧文明は、マルクス以来の「帝国主義的歴史観」を脱することができる。
そして、歴史の発展に人種的要素を拭い去ったことで、人種的偏見からも脱している。倫理的な意味でも西欧社会は他地域に比べ先進的である。著者の議論には、こうした意図や思惑が透けて見えるような文に度々出くわす。
例えば、著者は人種的説明に関して、日本を引き合いに出し、日本のような国では今でも文明の発展の差を人種的要因に帰する説明が無条件にまかり通っているのだという。こうした見方自体、非常な偏見だと思うのだが、著者にはそのような自覚はなさそうだ。
西欧文明がなぜ先進的な文明をもたらし、世界の富と生産力を保持することになったのか、というそもそもの立論自体に非常に違和感を覚える。結局そこから出てくる答えは、西欧文明が世界に対して支配力、影響力を持つことの正当化でしかない。人種的偏見を積極的に乗り越えたかのように喧伝する一方で、植民地化、奴隷貿易、原住民の虐殺などの歴史を発展の必然と見做すような裏の意図が見え透いてしまう。
このような著者の仮説を見ていくと、本書がアメリカでさまざまな賞を受賞し、非常に評価された理由が見えてこなくもない。穿った見方かもしれないが、著者の論理立ては、アメリカおよび西欧社会の正当化に寄与していて、大衆の無意識的な罪の意識をうまく払拭しているように見える。その意味でアメリカなどでは非常に歓迎される議論なのだろう。
大著で専門的な内容であるにもかかわらず、アメリカで非常な売り上げを記録し、さまざまな賞を受賞した理由には、このような西欧の自己正当化が働いていたように思える。本書は、著者の議論のそうした性格を念頭に入れた上で読み進める必要があるように思う。
しかし、この点を差し引けば、銃、病原菌、鉄が人類の歴史を左右し、大きく動かしたという着眼点は非常に面白いものだ。
歴史の正当化というのは、どの国もやるものだ。日本も例外ではない。歴史には史観がつきものだということを十分わきまえていれば、本書は非常に面白く読めるものだと思う。
日本に関する新章
原著では、日本に関する章が新しく追加されているが、本書では訳出されていない。原著で参照してみたが、日本人から見ればそれほど目新しいことは書かれていない。
ただ、日本がナショナリズムにこだわるがゆえに、歴史学的、考古学的な議論を受け入れられていない、といった著者の理解には疑問を感じる。日本人の起源が韓国、中国(特に雲南)、東南アジアといった広い地域に渡っていることは当然のことだろう。
浩瀚な書物だが、読んでいて最後まで飽きさせない面白さはある。だが、非西欧社会はなぜ技術の進歩が遅れたのか、産業の発展がなかったのか、政治的に支配される立場となったのか、という問題提起の仕方には最後まで納得がいかなかった。
地域の差を発展の差として理解することそのものが、そもそもの間違いなのではないだろうか。著者の議論は、一元論的な発展史観に陥っているように見える。また、人種的な要因に還元する議論を一見乗り越えているかのようで、そもそもの前提に差別的な違和感を覚える。
地域差を発展の差としてではなく、純粋に多様性の差として理解する発想が初めからあれば、本当の意味で人種的議論から離れた歴史を語ることができたのではないだろうか。